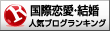僕の名前はダイ(仮名=25歳)。パタヤの夜遊びにはまって早や2年が経つ、言わば旅行者くずれだ。もちろん、夜の女の子が満足する程のお金を、僕は持ち合わせてはいない。それでも、あの手この手を使っては、女の子を口説き夜遊びを繰り返している。そんな僕が、毎日欠かさず実践している日課はこうだ。
日中は、38℃を越える猛暑でも我慢、打ちつけるほどのスコールに遭遇しても我慢、とにかく街を徘徊すること。そして、夜はどんなに疲れていても、どんなに酔っ払っていても一通りバービアを回ること。これは、「いつ、どこで可愛い娘に巡り会えるかは分からない」と、運命の出会いを信じる僕なりの哲学から来た行動である。そして、日夜問わずヒマさえあれば、知り合いの女の子にマメに携帯メールを送る。
送る内容は大体決まっていて、「I miss you…」だとか「I want to see you…」とか単純なものばかり。僕はこのメールのことを自分で、「キットゥング・メール(キットゥングはタイ語で恋しい)」と名付けている。でも、このキットゥング・メールが、ヒマしてる女の子には結構うれしいものであるらしい。10人の女の子に送れば、その半分くらいは返信、あるいは電話をかけてくるのだから不思議なものである。
そして、ある晩のこと。行きつけのバービアに赴くと、いつものように、ビール片手に何人かの娘にメールを送り、その返信を待っていた。送った内容は「where are you? I miss you…DAI」。一番早く電話がかかってきたのは、最近、最もお気に入りの娘ロン(仮名=21才)からだった。でも、僕はロンがこの日ファラン(欧米人)の客と一緒にいる事を、さきほどロンの働くバーの娘から聞いていた。僕は電話には出ず、再びメッセージだけを送り返した。「I want to see you now...」。
その5分後。彼女から返信が来た。「I want to smoke U ! and Boomboom with U !」(あなたのモノをくわえたい、あなたとやりたい)と。僕は愕然とした。彼女はこんな卑猥な言葉を使う娘ではない。更に、彼女が英語が堪能ではないことも分かっていた。僕は考えた。おそらく一緒にいるファラン(白人)の客が、僕をからかうために代わりにメッセージを送ってきたに違いない。僕はカマをかけて返信してみた。「I know you have “Falung” tonight」(今夜、君にファランの客がいることは知っているよ)。
すると、すぐに僕の携帯がメッセージを受信した。「Yes ! And she loves it ! SO AM I ! Happy “Chukwow”!」(そうだよ彼女は欧米人が好きなんだ!それは私だよ。君はオ●ニーでも楽しんでくれ!)と。ここから、僕とロンの客との間でのメール合戦が始まった。無性に腹が立った僕は、何とかこの外人をギャフンと言わせたかった。
僕はふざけてこう返信した。「Never mind ! but I’m interesting how much money you give her... Please give her ‘BIG TIP’」(僕のことは気にしないで。ただ気になるのは、あなたが彼女に幾らあげるかってこと。どうかいっぱいチップをはずんであげて下さいね)と。すると彼「Who are you ?」(お前はいったい誰なんだ!)。そして僕「I’m Japanese, then don’t forget to take “Condom”!」(僕?日本人だよ。ああ、あと彼女とはゴムをつけるのを忘れないでね!)。
この一言はかなり効いたようだった。そして、最後に彼は、日本男児を小バカにするような内容のものを返信してきた。「Why Japanese have small penis??」(なんで日本人はナニが小さいんだい?)。確かに僕のそれは人様に自慢できるサイズじゃない。ズバリ言われて、頭の中は噴火寸前だったが、ここで切れれば相手の思うツボだ。僕は冷静に対処した。
「Yes ! so I don’t need to give her money, but you have ‘Big One’, So you should give her ’Big money’!」(うん、小さいよ。だから僕は、彼女にチップをあげる必要がないんだ。でも、あなたは大きなモノを持っているんでしょ。じゃあいっぱい彼女にチップをあげなきゃね)。
さすがに怒りの沸点に達した彼は、すぐさまロンの携帯から僕に電話をかけてきた。なにを言ったかは、はっきり理解できなかったが、捨てゼリフのような言葉であることは確かだった。
そして、次の日、僕はロンに会った。彼女いわく、あの後、怒り狂ったファラン(外人)をどうしようも対処できなくなった彼女は、“ブンブン”も何もせずに、彼のホテルを後にしたとのことだった。そして、その事態を全く把握できなかった彼女は「何が何だかさっぱり分からない。あなたはいったい、あのファランに何を言ったの?」と困惑の表情で尋ねてきた。
僕は答えた。「マイ・ミー・アライ(何でもないよ)。But, That’s “SAMURAI SPIRITS” !!(でもこれが侍魂ってやつさ)」。彼女は、尚もわけが分からないという様子だった。
パタヤは、その昔、ファラン(欧米人)によって作られた街。道を歩けばいつでも、どこでもファランの壁にぶちあたる。そして、彼らの中にはアジア人を見下した態度をとるやからも少なからずいる。白人は、得てして‘背が高い、顔立ちがよい、そして金払いもよい’と3拍子揃っている。モテルのは当然のことだ。今の僕には、その3はない。それでも、僕はパタヤが好きだ。ファランがむせ返るほどいるパタヤが大好きだ。なぜなのかは分からない。でも、これだけは言える。 僕は誓う、僕はファランと闘う。そう、僕にも多少なりとも侍の血は流れているのだ。
「負けるな、日本男児!!」
そんな言葉を胸に、今日も僕の足先は、バービアへと向かっている。