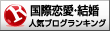「夜明けの空が瑠璃色(濃い赤味の青)に変わり輝くような思い出を僕にくれた北タイの妖精マイ。僕は幾多の問題を解決して、今、成田空港にいます。そして、これから君の住む街へと向かいます。あれから10ヶ月、、晩秋の風の匂いがあの日々の記憶を思い出させます。ふと風の声が聞こえます。マイはお前を待っていると―」。
彼女と過ごした甘いひと時もあっという間に過ぎ去り日本に帰国すると、僕には様々な問題が待ち受けていた。だが、変わらぬ日本の社会の中で、ほんの少し変わっていけた自分がそこには居た。それは、いざとなれば逃げれる南国の優しさを知り、生活の糧を与えてくれる日本の良さを知り、何より、どう転んでも売られるような境遇にはない自分の恵まれた環境を知り、そして、立ち直るためにやり込めた自分に再び自信が戻ってきたということだった。
「マイ キットゥン レ ラックン ナ キットゥン マイ バーンナ」。身の回りの問題にようやくメドがたち初めてかけた国際電話では、電話口のママさんが「よくもそんな恥ずかしい言葉を…(笑)」みたいに周りに喋ると、キャーキャーする歓声に囲まれマイが出た。そして、もちろん言葉は通じなかったが、気持ちは通じた気がした。
だけれど、実のところ、僕は最低な人間なのかもしれない。当時の僕を可愛がってくれた上司の計らいで系列会社で働くことができるようになった。そして、あの日本の彼女が目の前にいた。かつて本当に愛した人、そして、今も尚。まだ、芯まで吹っ切れていない自分がそこにいた。「では、マイへの思いは何だったのだろう?」。「この思いからただ逃げるために利用しただけなのだろうか」。僕はワケが分からなくなっていた。いったい僕は何処へ向かおうとしているのだろう。そして、僕は1週間の休みを貰い、再びマイに会いに行くことを決めたのだった。
肌を突き刺すような木枯らしが吹く日本とは違い、穏やかな晩秋を思わせる風の中、再びチェンマイ空港に降り立った。今回の宿は、チャーリーパブカラオケに近い郊外の中華系ホテル。チェックインも手早く済ませ荷物を部屋に放り投げると、夕暮れも差し迫ろうかという田舎道の中、僕は走った。そして、あの田園のあぜ道をしばらく突き進むと、チャーリーパブが見えてきた。
走りすぎて息が切れて、、あと30Mぐらいまで迫ったときだったろうか。たまたま庭に出ていたであろうマイが僕を発見したらしい。その短い髪をすべて風になびかせ、まるで親を見つけた子猫のように走ってきた。そして、その勢いのまま僕に飛びついてきた。顔全体を僕にこすりつけて、「カワサキッ!!カワサキ~ッ!!」(旅先でのニックネーム)と何度も何度も僕の名を叫ぶ。あの強い瞳から涙がこぼれていた。
身振り手振りで、「みんな来なかった。でも、カワサキだけは本当に私の所にまた来てくれた」と激しくむせながら告げた。僕は、「本当に来てよかった」と思った。人生でこの時ほど来てよかったと思ったことはなかった。
そして、あの湖へ毎日のようにランチを食べに行った。中華系ホテルのスタッフも温かい目で僕たちを見守ってくれた。でも、ある日、僕は見てしまった。マイがいつも隠すように持っているノート、そこには何行にも連なる数字が書き込まれていた。「200 250 200 300 150、、、、、」。日付けと一緒に上から下までびっしりと何ページにも渡り書き込まれていた。それが何を意味するのかすぐに分かった。僕が来た日付けには数字は1つで「1200」と書かれていた。それは僕がママに支払った1日分の金額(チップ)。おそらく普段はショートタイムばかりなのだ。そのおびただしい数を見たときに、僕は固まってしまった。
もちろん彼女が売春を生業としていることなぞ気にしないと思っていた。「しかたなく売られてきた、そうだろ?」。でも、その物凄い数字群を見たときに、糞にも劣る当時の僕は言葉が無くなっていた。情けなかった。小さな小さな自分がそこにはいた。そして、あろうことか僕は、その夜マイに、「日本でしか僕は仕事がない。例えば君とは結婚できない。でも何回も通うことは出来る」などと告げなくてもいいことを言ってしまった。マイは変わらぬ優しい表情でただ「分かってる」と頷いた。自分自身に語りかけるように頷いていた。
帰国の日、「大した金額ではないけど、残りのお金を全部上げるよ」と言うと、「要らない!だから、また来て!」と答える彼女。「もちろん」と頷く僕に、前回のように暗い表情はもう見せてはこなかった。
釈然としない気持ちを抱えながらも日本に戻ると、あの日本の彼女が相変わらず目の前にいた。仕事も順調、、だけれども何かが違う。僕はいったいどうしてしまったんだろう。思うにマイは僕が暗闇にいたあの時、光を与えてくれた。でもマイは本当は僕に希望という光を見出そうとしていたんではないだろうか?今度は僕が。でも覚悟はあるのだろうか?せめて身請け?いや、その後どうするんだ?小さな自分はそんな事ばかり考えていた。そして、日々思い悩みながらもすでに答えは決まっていた。僕は幾ばくかの現金を半年以上かけて作っていた。とにかくこれを渡そう、それしか僕には出来ないから・・。
久しぶりに国際電話をかけた。でも、電話口の応対は「マイは出られない」の1点張り。言葉が通じない。「いったいどうなってるんだ!?」。そして、僕は突然何かが爆発したかのように思いに任せるまま、その翌日には成田空港にいた。
日本では再び晩秋を迎えたこの頃、同じように「異国の売春婦を好きだ」と話す僕に呆れるような顔で又あいそを尽かし去っていった彼女。そして、「会いに来て」、それが精一杯の願いとただ待っている異国のマイという女性。「僕は再び君の住む街へと向かいます。晩秋の風の匂いが、あの穏やかな甘いひと時を思い出させます。風にたなびく短い髪が、あの日の涙が、心に響き聞こえてきます。あの日の思いが…風の言葉が…。
チェンマイに着くと、早々にあの中華系ホテルへ。そこのボスが良い人で何かトラブルがあればいつでも相談してくれと前回泊まった時に言ってくれていた。彼は英語が堪能な中華系タイ人。僕とマイのことはもちろん覚えていて、「君の彼女が働いている境遇も知っている、僕に任せてくれ!」と快く事情を聞いてくれた。そして、僕は、先ずチャーリーパブカラオケに電話をしてもらった。
電話が繋がると、ほどなくして彼の表情が曇りだした。そして、数分の会話を終えると、彼はつぶやくように僕に告げた。「う~ん、タイ人じゃないなー」。「えっ!?」。「詳しい話が通じないんだ。ただ彼女は身請けしてもらったような感じの事を言っているような、電話では難しいなー、よし!そこに一緒に行こう」。「でも、そこまでしてもらうなんて」。「なーに、君は日本からそのためにここまで来たんだろう?僕はソンテウに乗るだけ。よく覚えているよ、幸せそうだった君たちを。さぁ行こう!」。
そして、彼の厚意に甘え2人でチャーリーパブカラオケへ。店に着くと、すぐにマイの友達たちが僕に駆け寄ってきた。それから「マイは、あの山のずーと向こうだヨ」と身振り手振りで示してくれた。西にそびえる山向こう、それはタイではない…と。そして、「幸せに結婚した」と指と指をくっつけて一生懸命僕に伝えようとしてくれた。
「でも、マイは本当はあなたと結婚したいといつも言っていた。マイは一番大切にしていたものがある。何だか知ってる?」と、彼女がいつも肌身離さず持ち歩き皆に見せていた宝物の話をしてくれた。それは「あなたと一緒に湖で撮った一枚の写真。マイはそれを大切に持って帰ったの。あなたが来たら、そう伝えて…」と。僕は涙が止まらなかった。
付き添ってくれた中華系の彼が言う、「ここの人たちは密入国だろう。多分、あの人たちは皆ミャンマー人、そういうシンジケートの人々だろう」。彼が尋ねたところによると、彼女の本当の名前は「スゥイラク」ということだった。ミャンマー人に苗字は無い。そう「マイ スゥイラク」とは「新しいスゥイラク」という意味。彼女は新しく生まれ変わり、タイという国で生きて行こうと決めたのだろう。そして、そうすることで辛いことにもぐっと耐え続けてきたのだろう。
僕の中で、ひとつの物語が終わった。マイはマイ(新しい)でない元のスゥィラクにきっと戻ることが出来たのだろう。眩しいばかりの笑顔を絶やさない君に…。ただ、僕の心の宝箱には静かに瑠璃色の光を放つ宝石を残して。
これが(本当の意味での)僕の旅人生の始まり、、そして、今も宝石を探す旅を続けています。たくさん増えた宝物たちの中でもお気に入りの瑠璃色の宝石のお話でした。(完)
【文提供/ビレッジK氏】
アジアをこよなく愛し、通い続けること早や30年以上。自由の地を探し求め続けるオトコ(50代)。職業は「トレジャーハンター(自称)」。国境地とか辺境地とか危険な地帯が好き。大好物はビアチャーン。心はピュアな助べえオッサン日本A代表。好きな食べ物:もぎたてアジアの果実/嫌いな食べ物:都会で売れ残った渋い果実。