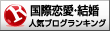「ドンッ、ドンッ、ドンッ、ドンッ…」
プノンペンの闇夜、人々のざわめき、艶かしく踊るディスコの女、周囲を飛び交う色鮮やかなレーザー光線、ズンッズンッと重低音の振動が身体全体に響き渡る。安宿の一室、暗がりの中、官能的に悶える女の顔、褐色の肌。長い黒髪を淫らに振り乱し、恍惚の表情を浮かべる。ギシッギシッと規則的なリズムを刻むベッドの軋み音。壊れた映写機のように断片的な映像が鮮明に浮かんでは消え、脳内に映し出される。
「ドンッ!ドン!ドンッ!ドンッ!」
映像が曖昧になっていく。瞼の向こうに微かな光を捉える。うっすらと目を開けると、薄汚れた灰色の天井で4枚羽のファンが不安定な音を立てて回っていた。ああ、そうだ、俺は今カンボジアに来ているんだった。おもむろに首を傾け隣りに視線を移すと、背中を丸めた裸の女性が毛布に包まりスヤスヤと寝息を立てていた。昨晩は何時に宿へと戻ってきたのだろうか。
「ドンドンッ!ドンドンドンッ!!ドンドンッ!」
部屋の向こうから激しくドアを叩く音が聞こえてくる。今何時なのだろうか、掃除婦がベッドメイクに部屋を訪れたのだろうか。二日酔いなのか鉛を詰め込まれたようにズキズキと頭の奥が重く痛い。ようやくベッドから起き上がり、下半身がヒリヒリと痛むのを感じながら、無造作に投げ捨てられたタオルを腰に巻く。
薄暗い室内で閉め切られたカーテンを開けると、ギラギラと眩しい朝の光が部屋中に差し込んだ。光を捉えた彼女は邪魔くさそうに毛布の中に身を隠す。部屋中に散乱していた昨晩の情事の残骸を簡単に片付け、入口のドアを開けると、ニコニコと微笑むエビスさんが立っていた。
「ようやく起きてくれましたか、、お早うございます!」
そう言うと、エビスさんはズカズカと部屋の中に入ってきた。僕は面倒くさく感じながらも、エビスさんに缶コーヒーを手渡され、窓際の椅子に腰を落ち着ける。テーブルに置かれた腕時計に手を伸ばし時間を確認すると、まだ朝の9時だった。寝ぼけた頭で昨晩の出来事を思い出し、エビスさんとあれこれ話し始めると、まだベッドで寝ていた彼女が恥ずかしそうに毛布から顔を覗かせた。
「あれっ、彼女、まだいたんですか?」
「は、はい、昨日はあれから一晩中ですかね。あのカマグラのせいですよ、ずぅっと痛いぐらいにギンギン状態が続いて…。寝たのは朝方頃だと思います。で、エビスさんの方はどうでした?」
「僕の子は一回終わったらすぐに帰ってしまいましたよ。プロっぽくてあんまり良くなかったですねぇ…」
ようやくベッドから起き上がった彼女はタオルを身に着け、床に散乱していた自分の下着と衣服を拾い上げると、いそいそと恥ずかしそうに浴室へと駆けていった。
「今日は行きたいところがあるんですよ。さぁ、ヒロ君も準備をして出かけましょう!」
3人で部屋を出ると、朝から容赦なく照りつける太陽の下、僕らはエビスさんを先頭に大通りを歩き、セントラルマーケットへと向かった。僕は忘れないうちにと、約束の20ドルを彼女の手に握らせた。彼女はその紙幣を確めることもなく、無造作にズボンのポッケに押し込んだ。
市場に到着すると、一緒に朝ご飯でも食べようと身振り手振りで意思表示し彼女を誘ってみたが、彼女は首を振りそれを拒否した。彼女はその辺の屋台でビニール袋に詰められた持ち帰り用のカンボジア料理を自ら購入すると、淡々とした表情で僕らに別れを告げた…。
エビスさんに連れられ、セントラルマーケットから出ていたオンボロのミニバスに乗り込む。車内では場違いな日本人二人に対し、同乗している現地の人々が訝しげな視線を投げかけてくる。昨日までの市内の街の喧騒とは異なり、明らかに郊外へと向かっているのであろう、ほどなくして車外の景色はのどかな自然が広がるだけになった。
「これは一体、どこに向かっているんですか?」
「プノンペンには有名な置屋街が2箇所あるんですが、今日行くのはスワイパーという置屋村です。あと通称70thストリートという延々2キロ程の売春宿が連なる巨大な置屋通りがあるんですが、そっちは最近、有名になりすぎたせいか取締りが厳しくなって閉鎖している店が増えているんですよ…」
「は、はぁ、、スナイパー?にセブンティーストリート?ですか。何だか西洋映画に出てきそうな格好いい名前ですねぇ!?」
「いやいや、スナイパー(狙撃手)じゃなくて、スワイパーですよ…」
映画好きの僕は、サムペキンパー監督の「砂漠の流れ者」やクリントイーストウッド監督・主演の「許されざる者」など西部劇に出てくるような荒野の中に佇む街並み、木造建築の売春宿といった古きよきアメリカ開拓時代の映画の情景をなぜか連想してしまい、期待に胸躍らせていたが、実際、到着してみると、そこは荒野に佇む街というよりは、時代に取り残された荒廃した村というような様相であった。
バスに揺られて20分ほど走っただろうか。スワイパー村に到着し、周囲にはそれ以外何も見当たらないような場所でバスを降りようとすると、他の乗客たちはどこか軽蔑するような視線で我々を見つめていた。僕らだけだと思っていた日本人の乗客は実は他にも数人いたことに驚き、そこでは日本人以外、現地の人は誰も降りないことに一種の羞恥心を感じた。
熱帯地方の炎天下、舗装もされていない赤土のデコボコした道路が広がり、掘っ立て小屋のような民家がポツポツと点在する田舎の集落。黄土色の景色をしたのどかな村というのが第一印象で、そこが売春村だとはとても思えないような所だった。
いざスワイパー村に入り、エビスさんに導かれるままに一軒のカフェ屋へ足を向けると、僕はその光景に更に驚愕した。その村で唯一の店なのかどうかは別にしても、店内にいる客はほぼ8~9割方が日本人だったからである。大多数の日本人が店内を占拠する中、数人の欧米人の姿もあった。
「欧米系はドイツ人が多いですねぇ、日本人とドイツ人は性格が似ていると言いますが、やっぱり性的嗜好も共通点があるんでしょうかねぇ…」とエビスさんは訳知り顔で僕に告げた。
竹製のテーブル席に腰掛けると、エビスさんの勧めでアイスコーヒーを頼む。グラスに氷が一杯に詰められ、練乳がたっぷりと入った何とも甘ったるいコーヒーで、熱帯気候の飲み物らしく、氷をシャクシャクと溶かしながら飲むのが定番なのだと言う。僕は強い日差しで瞬く間に汗だくになり、甘ったるいコーヒーも飲み始めるとすぐに氷が溶け出し丁度いい按配になった。
エビスさんは、ポッケからおもむろにカンボジア産のタバコを取り出し、僕に勧めてきた。中に葉っぱを混ぜたジョイントである。「こんなところで大丈夫なんですか?」、「大丈夫ですよ、周りの皆も吸ってますし、店員も何も文句は言いませんから」。よく見ると、周りの日本人たちも素知らぬ顔でプカプカと怪しい煙をくゆらせていた。裏で仕切っているのか、賄賂で繋がっているのか、悪徳警察官の姿もちらほらと見かけた。
ようやく、そのあり得ない光景にも慣れてきて、周囲を観察すると、僕ら以外は皆ほとんどが顔見知りのようだった。僕のような若者は少数派で、どう見ても個性が強いエロエロ、ロリロリの濃いキャラクターを持った中高年親父たちの集会のようであった。
大きなテンガロンハットをかぶったカウボーイ気取りのオッサン、一日何発できるかを大声で自慢げに話す男、村の全部の女を片っ端から制覇しようと目論んでいる男。皆が一様にタオルを首からかけたり、頭に巻いたりしている。車で乗り込み、土埃を巻き上げながら村内を周回する輩もいた。
「ああ、○○さん、今日は出勤が遅いですなー。オキニの××チャンはもう△△さんに取られちゃいましたよ」
「昨日は○○チャンで失敗したので、今日は先ずあの店の××ちゃんから流して、次に□□ちゃんに行きましょうかねぇ…」
カフェ店内の特等席(店の真ん前の席で通り沿い)に陣取り、小さな集落の中で仲間同士あーでもない、こーでもないとエロ談義に花を咲かせる。そうこうする内に一人、また一人と性戦に出かけては、30分程するとカフェに帰還して、再びあーでもない、こーでもないと終日にわたりロリ談義を繰り返す。
カフェから視界に入る店の女の子たちが、軒先から身を乗り出し、身振り手振り無邪気な仕草で嬌声をあげ、こちらへ誘いの言葉を投げかけている。お茶を飲みながら、のんびり椅子に腰掛けた男たちは笑顔で手を振り返し、それに応じる。
エビスさん曰く、彼らは決まって朝10~11時頃に村に出勤し、日が暮れる夕方5時頃まで(治安が悪くなる前)には街へと戻り、自分の拠点地に帰還する。そして、夕方からは定宿の食堂に集まり、宴会しながらその日の反省会という流れが毎日の日課となっているようである。
僕は目の前で繰り広げられる異様な光景と、嫌でも耳に飛び込んでくる男たちの会話に衝撃を受け、呆然とするだけだった。
ただ、しばらくすると、先程のジョイントが効いてきたのか、僕の脳内は熱帯の太陽にドロドロと溶かされるように思考が曖昧になり、その空間に支配され堕ちていくように身を任せるだけであった。
タイ移住生活14年間の放浪物語―フィクション50%+ノンフィクション50%=(ハーフ&ハーフ)ストーリー