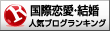カンボジアの首都プノンペンの郊外にひっそりと佇む置屋村スワイパー。ポルポト政権崩壊後、貧困に喘ぐカンボジアで1990年代に次々生まれたと言われる売春地帯の中で、悪名を世界に轟かせたその村には、各国を代表する性的嗜好者や小児性愛者といった好事家たちが訪れ、密かに闇の隆盛を極めていた。
僕がアジア好きの先輩エビスさんに誘われるまま初めてカンボジアを訪れ、その辺鄙な場所にある村へと足を踏み入れたのは、その村が2003年にNGOの介入と現地警察による摘発で壊滅した一年前、2002年のことだった…。
「さぁ、それでは我々もそろそろ行きましょうか!」
プノンペン滞在三日目、悪の巣窟のような売春村スワイパーに入村した僕は、先ずは様子見にと足を向けたカフェでエビスさんの置屋話に耳を傾けながら、甘ったるいアイスコーヒーで喉の渇きを潤していた。じりじりと身体全体を蝕む熱帯地方の熱気と、目の前の異様な光景にすっかり思考能力を奪われ、熱中症に侵されたような気だるさと偏頭痛を感じていると、エビスさんが出発の合図を僕に告げた。
エビスさんに連れられ、適当な店に入ってみる。取り締まりに対する用心のためか、鉄格子の門は人が通れる程のスペース以外は閉じられており、娼館の建物はコンクリート造りの2~3階建てと、周囲の木造民家との実入りの違いを主張しているかのようだ。中の様子が見えないスライドドアを開いて店内に足を踏み入れると、入口のすぐ脇に客専用のソファー席が置かれていた。
見るからに金に汚いヤリ手ババァといった風貌の店主に促されソファー席に腰を据えると、すぐに10人以上の女の子たちが店の奥から続々と現れ、僕らを取り囲んだ。皆キャピキャピ、ワイワイと威勢よく押したり、しな垂れかかったり、僕らの上に乗っかって来たりと、ものすごい圧力をかけてくる。ただ、それはパジャマ姿の無邪気な幼い子供たちの集団といった様相で、皆一様に白いパウダーを塗りたくった顔と真っ赤な口紅で嬌声をあげる姿は、ある種の不気味さを漂わせていた。
色白の小柄な子ばかりで、聞くとベトナム人が多数を占めているということだった。僕は数人の女の子に囲まれ、ベタベタと触られ、キスされ、瞬く間に顔中が白い粉と口紅で埋め尽くされた。僕はそれに喜びも性欲も感じることなく、ただ不快感を覚えるだけだった。どうにもその場から逃げ出したくなり、助けを求めるように隣を見ると、エビスさんは満面の笑みで女の子たちと戯れていた。
「わたしゃ、ブンブン、ニャムニャム、グー(Good)よー!」
タイ語なのか、カンボジア語(クメール語)なのか、よく分からないが、明らかに卑猥な言葉と仕草を投げかけ、ニコニコと微笑んでいる。女の子たちもキャーキャーとそれに反応し歓声を上げる。エビスさんは「じゃあ、ヒロ君、ここでやりましょうかー?」と恵比須顔で僕を誘い、「いやぁ、どうですかねぇ…」と僕が躊躇っていると、「まぁ、まぁ、そう深く考えずに3~5ドル程度ですので付き合ってくださいよー」と催促してきた。
付き合いだからと自らを強引に納得させ、幾分年を重ねた女の子を適当に選ぶと、スラム街を彷彿させるような薄暗く湿っぽい廊下を通り、小汚い共同の風呂桶の前まで案内された。辺りを見回してもシャワー設備のようなものはなく、粗雑に溜められた水の中にプラスティック製の桶がプカプカと浮かんでいる。
これで身体を洗わなければいけないのか…。日本ではあり得ない光景に動揺しつつも、どうにか覚悟を決め、女の子に身体を拭くためのタオルを要求すると、彼女は廊下の壁にかけられた、誰が使ったかも分からない、ボロ雑巾のような数枚のタオルを指差した。
「ああ、、さっき見た日本人の皆さんが一様にタオルを身につけていたのは、このためだったのか…」
僕はようやく理解した。浴室とは到底いえない、廊下に面した剥きだしの風呂桶の前で、僕は衣服を脱ぐと、遠慮がちに2~3回ほど少量の水をかけ、自分のTシャツで身体を拭いた。それからようやく部屋に案内されると、そこは小さな2~3畳ほどのスペースにベッドが置かれただけの、足の踏み場もないような一室であった。
「部屋は店から各々にあてがわれ、寝泊りもここでしているのだろうか…」、木製のベッドに装備された小さな戸棚には化粧品のほか、彼女と家族らしき人物の写真が並べられ、ベッドの上では数体のぬいぐるみが乱雑に居座っていた。部屋の片隅では彼女が脱ぎ散らしたであろう衣服が散乱し、そこで寝起きしている生活の一部が垣間見えた。
部屋を物色するように見回す僕をよそに、彼女は早く事を終わらせたいのか、白いパウダーを自らの顔に塗りなおし、香水らしきものを振りまいた。覚悟を決めたような表情で、彼女が僕に寄り添ってくる。石鹸やシャンプーの香りとは違う、鼻をつく独特の匂い。
僕はどうにもいたたまれなくなり、そこで行為に移ることを断念した。驚く彼女をよそに、再び衣服を身に着けると、受付で支払った以外の数ドルのチップを彼女に手渡し、その店を後にした。
僕はそれ以来、置屋やショートタイムバーと呼ばれるような場所を訪れる機会があると、あの店で感じた異様な空間をなぜか思い出してしまい、敬遠するようになった。あの鼻をつくような独特の匂いは、僕にとって置屋とかスラムを思わせる匂いへと転化され、それは陰鬱の象徴のようになった…。
先程のカフェで再び甘ったるいアイスコーヒーを頼み、エビスさんの戻りを待つ。
「僕にはここの雰囲気は無理みたいです…」
「そうですか、まぁ、しょうがないですねぇ。じゃあ他の店にでも行ってみますか?」
「いえいえ、僕はもう大丈夫です。ここで待ってるので、エビスさんだけでも楽しんでくださいよ」
事を終え満足げに戻ったエビスさんは、僕の話に残念そうな表情を浮かべたが、「じゃあ、ちょっと知り合いのところに行きたいので付き合ってください」と、村内の奥にある木造バラックの集落に僕を連れて行った。現地人が住む民家らしき簡素な掘っ立て小屋の一つに、その日本人はいた。
「えっ、こ、こんな所に知り合いは住んでいるんですか?」
「○○さんはプノンペン界隈では有名な日本人ですよ。現地のガイドをやったり、最近では指さし会話帳(カンボジア版)のコピー冊子を売ったりして小銭稼ぎしているらしいです。スワイパーを訪れた旅行者に結構売れているみたいですよ、安いのでヒロ君も買ったらどうですか?まだカンボジアにしばらく滞在することだし、何かと役に立ちますよ」
「は、はぁ、、そうなんですか…」
なんとも逞しい男だ。ていうか、こんな辺鄙な所によく住めるもんだと僕は衝撃を受けたが、彼がロリ嗜好の置屋大好き人間ならば、ここは天国のような場所なのだろう。エビスさんが彼の名前を呼び続けて、数分後、薄汚れた衣服とボサボサ頭の男が寝起きなのか面倒くさそうな面持ちで、掘っ立て小屋から姿を現した。
エビスさんは「お久しぶりですー!」と元気に挨拶を交わすと、日本から持参した数種類の即席麺をリュックから取り出し、手土産にとその男に渡した。とたんに彼は喜び、「じゃあ、その辺で肉と野菜でも買って、これで宴会でもしましょうか?」と提案してきたが、「いえいえ、腹は減ってませんから大丈夫です!」とすぐに僕は拒絶し、エビスさんに伝えるように彼に告げた。
それ以外、僕は彼らの会話に加わることもなく、ただ早くホテルへ戻りたい、この場所から立ち去りたいという思いに支配されていた。エビスさんは久しぶりの旧友に再会したように彼との談笑を続け、最近のプノンペン事情についてあれこれと質問し、男の話に耳を傾けていた。
「じゃあ、そろそろ行きましょうか?ヒロ君、この後はどうします?」
「いやぁ、僕はもう十分なので、エビスさんがまだ遊びたいなら、僕はまたあのカフェでお茶でもしながら待ってますけど」
「そうですか、じゃあ、ヒロ君にも悪いし、僕はホテルに連れて帰る子でも探しましょうかねぇ」
再びデコボコした赤土の道路を練り歩く。村内のあちこちで真昼間から行われている屋内での秘め事を除けば、そこは昭和初期を思わせるような牧歌的な田舎の光景がのんびりと広がる空間である。
木造民家の軒先で、小学生ぐらいの子供たち数人が、赤ん坊を抱いた母親と祖母らしき人物に見守られるように、自転車に跨り、無邪気に遊んでいた。「ああ、こんな環境の中で普通の人たちも暮らしているんだ…」、その様子を微笑ましく眺めていると、エビスさんが悪魔のような言葉を僕に囁いた。
「あれぐらいの子でも出来るんですよ」
「えっ、まさか、嘘でしょ!マジで言ってるんですかぁ!?」
「いえいえ本当ですよ。あそこに一緒にいる母親に交渉すれば多分大丈夫なはずですよ。あれぐらいの年頃の子でもすでに経験しているはずですから。もうヒロ君も帰りたいようだし、また探すのも面倒だから、ホテルに連れて帰るのはあの子にしましょうかねぇ…」
「え、えーっ、、嘘でしょ、、マジで言ってるんですか…」
不敵な笑みを浮かべたエビスさんが、母親らしき女性の方へと歩み寄り、臆することなく交渉を始めると、彼女は辟易するような顔を見せて、それを拒否した。すると、隣にいた婆さんが急に場を仕切り始め、何やら周囲に呼びかけるように大声で怒鳴ると、しばらくして、一人の女の子が我々の前に姿を現した。
エビスさんは、もはや悪人面に変わり果てた婆さんと何やらゴニョゴニョと話し始めると、「30ドルと高額ですが、この子だったらOKみたいですので、持ち帰りはこの子にしましょうかねぇー」と、あっけらかんと僕に告げた。どう見ても、小学生高学年ぐらいの年頃の女の子だった。僕にはそれを止めさせる権利などあるはずもなく、ただ、その異質な光景を目の当たりにして、吐き気を催すように、うな垂れるだけだった。
さすがに一緒に連れて帰るのは危険だということで、あとで送りの者がホテルの部屋まで彼女を連れて来てくれるようだ。帰りはバイクタクシーで直接ホテルまで戻ることになった。灼熱の太陽の下、のどかに伸びる一本道を疾走するバイクの後ろで、僕は舞い散る土埃に顔を覆いながら、グニャグニャと変化する風景の中、奇妙な夢を見ているような感覚に襲われていた。
「じゃあ、僕はちょっと一眠りしますので、また夕方頃、食事にでも出かけましょう…」
衝撃の時間を過ごし、ようやく宿に到着すると、僕は早く解放されて部屋で休まりたい一心で、スーパーへ買出しに行くと言うエビスさんの誘いを断り、一旦別れを告げた。
ずっしりと重い疲れを身体に感じながらも、定宿に戻ってきた安堵感からか、ホテルの階段を一気に駆け上がる。
僕が寝泊りしている奥の角部屋まで、薄暗い廊下を早足で歩く。
部屋の前に置かれたアンティーク調の椅子に誰か座っているような人の気配を感じる。
ホテルに住む売春婦だろうか。甘い香水の匂いが漂ってくる。
僕を視界に捉えたその女はおもむろに椅子から立ち上がる。
暗がりの中、昨晩ディスコで出会ったスレイラの姿が現れた。
彼女は僕の反応を窺うように、恥ずかしそうに微笑んだ。
タイ移住生活14年間の放浪物語―フィクション50%+ノンフィクション50%=(ハーフ&ハーフ)ストーリー