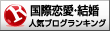もう何日パタヤに滞在したのだろうか…。エビスさんとカンボジアのプノンペンを訪れたのも遠い過去の出来事のようだ。甘い日々を過ごしたカンボジア人女性スレイラは、まだあのディスコに夜な夜な通い客探しを繰り返しているのだろうか。いかがわしい旅のガイド役エビスさんに従うように訪れたカンボジア10日間、それからパタヤ入りした後も色々とあったが、我々は2週間だった当初の旅の予定を1週間延ばした。
そして、僕をアジア(タイ)へと誘ったエビスさんも日本に帰国してしまった。僕は独りになったけれども日本へは帰らず更に1週間滞在を延長した。それから、エビスさんと入れ代わるようにして、タイ長期滞在者のリュウさんが現れた。シェフというアジアの放浪人とも一席共にした。リュウさんと夜の街を徘徊するうちにニックという親日家のアメリカ人に出会った。
異国の地でひとり孤独を感じていたのもつかの間の一時であったかのように、僕は目まぐるしく日々出会う男たちに巻き込まれるように、目的もなくダラダラと惰性でパタヤに居座った。どこか他の土地や国へ旅に出かけるような気力もなく、かといって日本に帰りたいわけでもない。いや、とにかく、今はまだ日本には帰りたくない。ただ甘えるように南国の穏やかな空間に身を委ねた。のんびり気楽に今を生きている民族タイ人に影響されるように、だが、その日、その日を追われるように、毎日を刹那的に過ごした。
そんな僕をよそに、時計の針は当然のように淡々と時を刻んでいく。日本を飛び出してから、早や一ヶ月が経とうとしていた…。
飛行機はオープンチケットなのでまだ問題ないが、東京の一人暮らしのアパートの家賃をそろそろ大家に振り込まなければならない。久しぶりにインターネットカフェに出向いて、メールチェックがてら、弟にでもお願いするしかないか。田舎の両親にはもう色々とバレてしまっているのだろうか。
それに滞在査証の問題もあった。カンボジアからタイへ陸路で入国した僕のパスポートはノービザのスタンプを押されていたから、そのうち滞在有効期限の30日を迎えることになる。それまで一ヶ月以上タイに滞在したことなどないのだから、どう処理すればいいのか全く分からなかった。どこかで滞在を延長できるのか、あるいは日本にとうとう帰国しなければならない時が迫っているのか。現実に目を向けると、色々と頭を悩ます問題が次々と、当然のように我が身に降りかかってきた。
パタヤの長期滞在者リュウさんに紹介してもらったLEKアパートメントに定宿を鞍替えした僕は、新しい宿に移動してきた喜びもつかの間、窓辺の椅子に腰かけ、煙草を燻らせながら、今後についてあれこれ思案していた。通りに面した角部屋の窓を開けると、3階からの眺めはダイアナ通りを行き交う人々を頭上から眺めるのにちょうど良い距離感だった。僕は宿隣りの生活雑貨店から買い出してきた缶ビールを飲みながら、のんびり午後を休息するように過ごした。
「コツン、、、コツン、、、ゴツッ!!」
いつの間にか眠ってしまっていたようだ。何かが窓に当たるような物音が聞こえ、目を覚まし、窓際まで歩み寄る。通りを見下ろすと、下からリュウさんがこちらを見上げて、今まさに何かを投げようとしているところだった。どうやら小石を投げて窓に当てていたらしい。僕に気づいたリュウさんが手を振る。辺りはすでに穏やかな茜色の夕陽に染められていた。
「ああ、すいませんー、すぐ行きますー」。
今晩もリュウさんと出かける約束をしていたんだった。テーブルに置かれた腕時計を確認するとすでに18時を回っていた。すぐに準備を整えて、階段を早足で駆け下りる。部屋まで来てくれればいいのに、なんで石を窓に投げるなんて原始的なことをしていたのかと不思議に思っていたが、3階から階段を下りながら、ああ、階段を上がって来るのが面倒だったのかと合点がいった。
「どうもすいません。今日は昼頃こっちに引越してきて、部屋でダラダラ過ごしてたんですが、つい寝てしまって。それよりさっき石か何か窓に投げてたでしょ?ゴツッってすごい音しましたよ…」
「ははは、そうだった?ごめんねー。ここ部屋に電話もないし、3階まで階段上がるのも面倒だったからさー」
それから、リュウさんは遊びの誘いに来る子供のように、毎日夕方6時頃になると僕の宿を訪れるようになった。初めは少し煩わしいなと感じていた僕だったが、エビスさん帰国後の独り身を埋め合わせするようにリュウさんの誘いに応じ、彼と街へ繰り出し、毎晩のように飲み明かした。
アメリカ人のニックにも度々会うようになった。彼は2週間のパタヤ滞在とのことだったが、僕らがバービアで飲んでいると、不思議と毎晩のように色々なエリアで遭遇し、その後は3人で飲み歩くことになった。僕と一回り近く年上のリュウさんに、そのまた更に年上で親父と言ってもおかしくない年齢のアメリカ人ニック。奇妙な組み合わせだが、僕は二人の男に我が身を委ねるようにして時を過ごした。
リュウさんの滞在先にもお邪魔するようになった。ソイブアカオのパタヤカン(中央)寄りにあるホリデイという長期滞在者向けのホテルだった。週単位、月単位の料金設定があり、リュウさんが滞在している部屋は5階建ての4階で、家賃は一ヶ月9,000バーツ程だという。水道代はそれに含まれていて、別途、使用した分の電気代を徴収されるとのことだった。それでも一日あたりに換算すると300バーツ程度で部屋を借りていることになる。僕が泊まっている安宿の方が350バーツと高いのに、そこは段違いの好環境であった。
数年前にできたばかりという建物はまだ十分に真新しく、ワンルームタイプの室内は申し分ない程度に広い。テレビ、冷蔵庫、エアコン、クローゼット、鏡台など、シンプルな設備ながら小奇麗にまとまっている。何よりいいのはベランダに出ると、プールを見下ろす景色だった。敷地中央に横たわるプールを囲うように宿泊施設が並んでおり、のんびりプールサイドでくつろいだり、泳いだりしている欧米人や連れの女性たちを眺めていると、ちょっとしたプライベート風リゾート空間を感じることができた。
僕は昼間にパタヤビーチへ足を向けることもなくなり、リュウさんのホテルを訪ねるようになった。午後の眩しい陽光を浴びながら、プールサイドの木陰でくつろぎ、取りとめのない雑談を繰り返す。リュウさんは関西人らしく話好きで、一度話し出すと止まらない漫才師のネタ話のように会話し、必ず最後にオチをつけることが重要なようだった。僕らはお互いに自分のことを語り、瞬く間に距離を縮めていった。
リュウさんはかつてプロボクサーだったらしい。30歳を機に身体の衰えから引退を決意した彼は、今度は自らの手でチャンピオンを育てる夢を抱き、プロのトレーナーになるため、本場のアメリカやメキシコを放浪し、現地のジムを渡り歩いた。そして数年後には日本に戻り、現役時代お世話になっていたジムでトレーナー業を始めた。しかし、海外を見てきたリュウさんにとって、日本の環境は刺激が足りなかったようだ。
そんな折、友達であるアジアの放浪人シェフからタイ行きを誘われた。タイはムエタイ発祥の地で格闘技王国でもある。興味を抱いたリュウさんはバンコクを訪れ、過去に世界王者を輩出したボクシングジムなど色々なジムに足を運んだ。そして、日本のボクシング関係者や知人のコネを辿り、タイ人のプロモーター(興行主)と知り合うことになった。リュウさんは日本向けに試合相手のタイ人選手を斡旋、仲介するプロモーターの仕事を手伝うようになった。それから2年をバンコクで過ごした。
しかし、お世話になっていたプロモーターが、ある試合の判定を巡り、敵陣営から恨まれることになり、暗殺されてしまったという。それを機にリュウさんはバンコクを離れて、程なく近い街パタヤに流れてきた。今は次にやりたいビジネスが幾つかあるから、それに向けて準備を進めている最中だという。
また、日本にリュウさんのことを応援してくれているスポンサーのような人物がいて、資金を出すから日本食レストランかタイマッサージ店をやりなさいと言われているらしい。僕は異国の地で耳にするビジネスとか、スポンサーといった大そうなワードに懐疑心を抱きながらも、羨望するようにリュウさんの話に耳を傾けた。
ソイブアカオの中程に日本人長期滞在者たちが集うバービアの集合施設があった。駐車場ぐらいの大きな敷地に簡素な屋根があるだけの巨大倉庫のようなスペースだが、左右20軒近くのバービアが軒を連ねる、風通しの良い開放的な空間である。広々とした敷地内には各店、ビリヤード台が置かれており、全て無料で利用できる。場末らしくドリンク代も繁華街に比べると格安で、深夜~明け方まで営業しているため、欧米人の長期滞在者でそこそこ賑わっていた。
パタヤに住む日本人長期滞在者は、その中の一軒に毎晩のように集っていた。「LITTLE ANT(リトルアント)」という名前のバービアで、小さなアリという名前そのままに、ボスは色黒で小柄なタイ人女性だった。彼女はクッキーというニックネームで、皆からは通称クッキーバーと呼ばれていた。クッキーにはイングランド人の彼氏がいて、彼が出資した店ということになるらしい。クッキーはビリヤードの腕前もピカイチだった。
店には色んなタイプとレベルの女性がいて、皆それぞれがビリヤード好きで、客の相手をしながら、様子を見ては賭けへと誘う。日本人長期滞在のオッサンたちも特にビリヤード好きが集っているという感じだった。学生時代、ちょっとした趣味でビリヤード場に通い、⑨ボールに興じていたことがある僕は、すぐにこのエリアが好きになり、バービアで流行の⑧ボールに夢中になっていった。繁華街へ足を向けることも少なくなり、ソイブアカオ周辺の場末バーを飲み歩くことが多くなった。
リュウさんと知り合い一週間ほどが過ぎた、ある晩のことだった。
相変わらず、リュウさんに連れられるまま、深夜遅くまで飲み歩いていた僕らは、最後の締めにとクッキーバーに寄り、カウンター席で肩を並べて、深い泥酔状態に浸っていた。そして、その言葉は突然、何の脈略もなく、リュウさんの口から僕に向けて発せられた。
「ねぇ、ヒロ君さぁ、、何か俺に隠してることない?」
僕はその言葉にドキリと反応した。僕はリュウさんに自分がテレビ関係の仕事だということは伝えていたが、辞めたことまでは教えていなかった。特番が重なったこともあって、久しぶりに一ヶ月も休暇をもらえたんですよ。とウソをついていた。しかし、パタヤから一向に帰る気配を見せない僕を彼が不思議に思うのも当然のことだった。いや、もしかしたら、僕自身からどんよりとした虚無感とか焦燥感といったような陰鬱な影が滲み出ていたのかもしれない。僕はとうとう本当のことをリュウさんに打ち明けた。
「実は、仕事を辞めて、タイに来たんです…」
「やっぱり、そうだったかぁ。いやぁ、もうパタヤにも長く居るし、日本に帰国する感じもないし、おかしいなぁと思ってさぁ」
「本当は仕事を辞めて、フラフラしている時にエビスさんに誘われてタイに来て、、1、2ヶ月滞在したら、日本に戻ってまた何か仕事を探そうかなとは考えているんですが。まだ、どうするか全く決めてないんですよ…」
「そっか、そうだったんだね。いやぁ、正直に話してくれてありがとう。でも、俺も若い頃は色々と職を転々としたからさぁ。まあ、ゆっくり考えればいいんじゃない」
「そうですかね、ありがとうございます…」
「東京に戻ってどこか次のあてはあるの?」
「いえ、何もないことはないんですが。でも、もうテレビの仕事は嫌なので、どうしようかという感じですかね。これを機に田舎に戻ろうかなとも考えてますし…」
「そっかぁ、じゃあ、今は日本に帰っても特に何も決まってないんだね?」
「そうですね…」
「まあ、例えば、もしヒロ君がタイに住んでも構わないっていうんだったら、俺の仕事を手伝ってもらうってのはあるんだけどねー」
「えっ、何なんですか、それって?」
「いやさぁ、俺もそろそろタイで何かビジネスを始めるつもりなんだけど、ヒロ君のような若い人材がいれば助かるからさー。大学も出てるようだし、テレビ局で働いてたなんて、いろいろ経験もあるだろうからね。あれだったら、俺のスポンサーにも話して、こっちで生活できるぐらいのサラリーは保障するからさー」
「えっ、マジで言ってるんですか?」
「うん、もちろんマジだよ。ちょっと本気で考えてみてよ。とりあえず1年でも2年でもいいからさー」
「あ、ありがとう、ございます…」
僕の瞳からは、とめどなく涙が溢れ零れ落ちていた。何をやっているのかもよく分からない、信用できるかどうかさえ分からない男、一体どんな仕事をするのかも具体性がなく信憑性もない話。だが、リュウさんからの甘い誘惑は完全に僕の心を射抜いた。窒息しそうになっていた心の扉が一気に開放されるような感覚に包まれた。
この男に全てを委ねてみようか。このまま行き当たりばったりの流れというものに我が身を任せてみようか。どうせ日本に戻っても、今は何もやりたいことなどないのだ。だったら1年、いや2年、3年、、30歳ぐらいまでなら、自分のやりたいようにバカをしてもいいのではないか。もし失敗しても30歳までなら、取り返しもつくだろう。そうだ、30歳までなら…。
両親はきっと怒り狂うだろう。勘当されるかもしれない。
でも、僕の頭の中はすでに夢にまで見た南国の楽園パタヤ移住という誘惑だけに支配され、ただ実現化に向けて、あれこれと現実的な問題に思いを巡らすだけだった。
タイ移住生活14年間の放浪物語―フィクション50%+ノンフィクション50%=(ハーフ&ハーフ)ストーリー