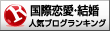「もう少ししたら日本に帰る。そしたら実家に電話して、これまでの経緯を全て話すから。父ちゃん母ちゃんには、あともう少しだけ待ってくれ、と伝えてくれ。よろしく頼む…」
久しぶりにインターネットカフェに行きメールをチェックすると、何日も前に弟からメッセージが届いていた。どうやら母親が東京のアパートに何度か電話したが繋がらない、折り返し連絡もないことから当然のように不審に思われたようだ。タイに持参している携帯電話は電源が切れている状態なので益々怪しい。そこで母親は弟に尋ね、問い詰めたところ、実は僕が数ヶ月前に会社を辞めたことから、今タイに行っていることまで、全て白状したという流れである。
それは簡潔な文で「とりあえず連絡しなさい!」というお怒りの催促メールだった。
「もう少ししたら日本に帰る。そしたら全て話すから…」。僕も簡潔な内容の両親宛のメールを弟に返信した。しかし、それまで僕を覆い尽くしていた焦燥感はもはや影を潜め、そこにはある種の決意に満ちた思いが込められていた。
仕事を辞めてフラフラ都会の雑踏で彷徨っていた時に、タイ好き仲間のエビスさんに誘われ、再訪したタイ、愛着の街パタヤ。それからエビスさん帰国後にタイ長期滞在者のリュウさんに出会った。僕は彼の住む世界や生活の一部を垣間見るように覗き、体感し、のんびり陽気な流れの中に我が身を任せるように時を過ごした。
リュウさんは話し好きの世話好きという感じの人物だった。日本を逃げ出しアジアを流離っているような孤独感が常に付きまとっていた、その時の僕にとって、リュウさんはまさに都合のいい日本人の飲み仲間のようで、頼もしい現地のガイド役でもあった。何しろ節約しながら安く滞在できることが、資金も底をつき始めていた僕にとっては有難かったし、何より心地よかった。
そして、お互いを語り、知り合う内に僕らは瞬く間に距離を縮めていった。一回り近く年上のリュウさんに、僕は友達というよりは先輩とか兄貴のような感情を抱くようになった。破天荒で波乱に満ちた人生ドラマのような彼のこれまでの半生を聞き、なんと物語のような人生を生きているんだと羨ましく感じた。
それは時を同じくして出会った親日家のアメリカ人ニックにしてもそうだった。元ネイビーで世界各国を渡り歩いてきたニックの人生物語は、日本人の僕にとってかなり新鮮だったし、アメリカ人の彼が語る人生観や価値観が至極自由気ままで大らかであることにひどいカルチャーショックを覚えた。羨ましさと共に、同じ人間なのに人種が違うと、お国が違うと何とここまで人生の考え方(捉え方)が違うのかと衝撃を抱いた。
彼らのこれまでの半生はまさに物語のようで、聞いていて面白かったし、更に興味をそそられ、想像を掻き立てられるドラマのようだった。それは例えば「俺がお前ぐらいの時は丁度イタリアに数年いた頃でブロンドのイタリア美人と恋に落ちていたんだ…」と語るニックの船乗り時代の思い出話や、「俺がヒロ君ぐらいの年の頃は30歳を前に引退を感じ始めた頃だなぁ…」とボクサー時代を懐かしむリュウさんの人生物語などである。
映画のような人生を歩んでみたい。それは僕の理想とする人生観だった。
そう思うようになったのはいつ頃からだろうか…。
福岡の片田舎で男ばかり三兄弟の次男坊として生まれ育った僕は、小中高と計12年間みっちりサッカーに明け暮れる少年~青年時代を送った。小学校の卒業文集に書いた将来の夢はプロサッカー選手であったが、それも高校生になり自分の実力やプロへの現実というものが理解できる年頃になると、夢より現実に生きようとする自分へと変化していた。
そして、大学への受験戦争、僕は現役での受験に失敗し、絶望にも似た敗北感に苛まれた。進学校だった周りの友達たちは半分程が各々の希望する大学に受かり、一方、僕と同じく受験に失敗した連中はほとんどが浪人生になり予備校に通うという雰囲気だった。就職を選択する者はほぼ皆無だった。当時、隆盛を極めていた代々木ゼミナールや河合塾などの大手予備校に通い、翌年の再受験を選ぶのが周りの常識だった。
僕は受験勉強より「浪人」という言葉の響きがひどく嫌で予備校には通いたくなかった。浪人とは現役合格した勝組たちから1年遅れをとること。それまでまっしぐらに進んできた人生という名の線路から脱線してしまったような状態(期間)。僕がこれまでの人生で初めてやるせない敗北感を覚えたのが浪人であり、それはまさに社会からのドロップアウトという感覚であった。
そこで僕は海外志向があったことから、思い切って両親に「浪人するなら、どっかアメリカかオーストラリア辺りにワーキングホリデーみたいな感じで海外留学してみたいんやけど…」と打ち明けてみたが、問答無用で却下された。田舎の両親にとって海外とは危険に満ちた知らない異国の地であり、留学など全く荒唐無稽な話というわけだ。それより、なにより、両親が僕に期待していたことは、地元の大学に行って、その後、親父同様の一流企業に就職し、立派なサラリーマンとして日々仕事に邁進すること。そのうち結婚して子供を作って、という至極一般的かつ昭和的な日本人の人生観であった。
僕の親父は頑固な性格の九州男児で、第二次世界大戦後のベビーブームで生まれた、いわゆる団塊の世代というやつである。その子供である僕は団塊ジュニア世代で、昭和の高度経済成長とか好景気というものを田舎の少年時代に何となく体感しながら育ち、やがて受験戦争、就職氷河期といった時代の流れに巻き込まれるように、大人への階段を上っていった。
まだ就職などする気もなかった僕は、周りの失敗組同様、あえなく再受験する道を選び、河合塾に通うことになった。しかし、脱落者だと感じていた浪人生活は僕の思考にゆとりを与えてくれる1年でもあった。予備校には東大や医学部を目指すような頭のいい真面目組から、授業をさぼってパチスロや競艇などのギャンブル、酒に溺れる連中まで色々いた。九州各地の地方から集まった大量の寮生に、二浪三浪、はたまた四浪まで何年も予備校に居続ける輩。そして、様々なキャラクターの講師陣たち。特に塾生たちに人気のある高額サラリーのやり手講師は毎日、飛行機で全国各地の系列塾を飛び回るような時代だった。
そこは人生の縮図のようだった。
とにかく自由を手にしたかった僕は、一人暮らしに憧れるようになった。そして、再受験する際、九州を離れて関西、関東方面の大学を選んだ。それは僕が初めて両親の期待を大きく裏切る行為であった。母親は何とか理解してくれたが、親父には結局最後まで言えず、受験票が届いた段階でその事実を知った親父は激怒し、愕然と肩を落としていた。
何とか親父にも許してもらえるような大学に収まった僕は、晴れて親元を離れて東京で一人暮らしを始めることになった。田舎者の僕にとって憧れの街、花の都、大東京は眩いぐらいに煌びやかで、とはいえ犯罪や危険に怯える落ち着かない街でもあった。
そして、学生時代に始めたテレビ局でのバイトが全ての始まりだった。高額だが特殊な類のバイトは大学をある程度おろそかにしなければならず、いつしかバイト中心の生活になり、大学2年にもなると僕は全く学校に通わなくなっていた。
自由な時間と空間を手にした喜びから、どっぷり映画や音楽などサブカル系の趣味の世界に没頭するようになり、影響されていった。映画の主人公や大好きなロッカーのような生き様に憧れを抱くようになった。いつしか僕は、自分の好きな分野で仕事をしたいと思うようになった。とはいえ僕はかなり落ちこぼれていた。大学ではクラスほぼ全員がゼミに入っているのに僕だけ入っていない。授業にも全く出ていない。僕は毎日真面目に授業に出ている数人の友達に代返をお願いしたり、テスト期間が迫ると連絡をもらいノートをコピーさせてもらった。全て羽振りよく金をばら撒いていたので、それは彼らにとっても好評で皆、協力的だった。
大学3年になり当然のように周囲が就職活動を始める中、僕は醜い単位の数に頭を悩ませていた。やばい、このままいったら留年コース間違いなしだ。高額な授業料を払ってもらっている田舎の両親に全く合わせる顔がない。最終年の4年になると周りの皆は就職先が決まりだし、余裕をもって学校に通い、残り少ない単位をのんびり取得する。一方の僕は2~3年分の単位を一気に取得しなければならず、周りの皆からすれば僕は確実に留年するだろうと思われていたようだ。僕は4年生の1年間、下級生たちに囲まれながら、あくせく学校に通い、何とかギリギリで卒業することが出来た。しかし、卒業は出来たものの、はたして就職活動には失敗した。
就職先を決める際、僕にとって最も重要だったのは、「毎日スーツを着なければならない仕事には就きたくない」ということだけだった。理由は単純でとにかく、あの首を締め付けられるようなネクタイが大嫌いなのだ。しかして農学部だったくせに畑違いの、好きな分野である映画・音楽業界ばかりを10社ほど就職希望先に選び、見事に全滅した。
これで浪人時代から数えると、僕はトータル2年も同世代の人達から遅れを取ることになると人生2度目の敗北感に襲われた。結局、僕はバイト先のコネを頼りに仕事を得ることになった。それはテレビ局に出入りする業者、テレビ番組の制作会社だった。仲の良かった取締役のおじさんが僕のことを気にかけてくれていたようで、「就職先がないんだったら、うちに来いよ」と誘ってくれたのだった。
僕はとりあえず、その会社に入れてもらい、数年後でも何かやりたい仕事が見つかれば転職すればいいさ、と自分に言い聞かせた。いや、ゆくゆくは映画や音楽業界に進みたいのだから、テレビも同じ映像(エンターテインメント)の世界ではないか、これは修行期間のようなものなのだと自らを納得させた。サッカー漬けの青春時代を過ごしてきた僕にとって、スポーツ番組を取り扱う仕事は実際、興味のある分野でもあった。
しかし、今までブラウン管の向こう側にあった華やかな世界に裏方として実際触れ、驚喜し、興奮を抱き、バブリーな学生時代の4年間を過ごしてきた僕だったが、それもいつしか色々と嫌な現実も垣間見るようになる。それはもう飽き飽きした感もある体育会系バリバリのムードであったり、煌びやかな世界の裏側にある札束が飛び交う大人のドロドロした社会であった。
悪口、噂話、嘘、建前、上司へのゴマすり、イビリ、イジメなどがそこかしこに蔓延し、金と権力と縁故が圧倒的にモノを言い、全てを牛耳っているような空間に身を置き続ける事に嫌気がさすようになっていった。地味な性格の自分にはこの業界は向いてないのではないかと思うようになった。
花の都だった東京生活は、いつしか息苦しい東京コンクリート砂漠へと変化した。
そして、僕は30歳を迎える焦燥感にひたすら怯えていた。それはいつからなのだろうか。20歳になり大人の仲間入りを果たしたような喜びに浮かれていたのもつかの間、自由気ままな大学生活を終え、一社会人として一企業に属し一会社員となると、当然のように、それまで子供の時にはなかった責任という名の重しを社会のルール、いや鉄則のように背負わされるようになった。それは僕にとってひどく窮屈なものに感じられた。
僕はきっと息苦しさに耐えられない性格なのだろう。何と子供の我がままのようなことを言っているのだろうと他人は嘲笑するかもしれないが、僕にとってそれは至極重要なことだった。
20代も半ばを過ぎると、僕の中の焦燥感は身体にまとわりつく化け物や浮遊霊のように巨大なものへと膨れ上がっていった。
「俺の思い描いていた人生とは、こんなはずじゃなかったのに…。でも、今ある現実が俺なのだ…。このまま周りの上司と同じように年を重ねていくのだろうか…」
30代、40代に自分がどのような仕事をしていて、どれぐらいのサラリーを手にして、ということは容易に想像できた。僕はその現実をどうしても受け入れたくなかった。ただ、自分で簡単に想像できる将来像に、何と退屈でつまらない人生なんだろうと辟易にも似た感情を抱いていた。
そして、そんな僕の思いを成就させるように、運命の女神はきっかけという悪戯を僕に仕掛けてきた。それは上司とのイザコザだった。昭和のサラリーマン全盛期にあくせく働いてきた親父世代から言わせれば、何を甘ったるいシミたれたことを言ってるんだ。上司に怒鳴られ揉まれながら、成長し年を重ねて、徐々に昇進していく。それから、ようやく課長、部長といった管理職になり、自分の意見が言える立場になるんだ。それが年功序列という社会構造なのだ。ということになるのだろう。
そこで我慢できた者が、ずっと一つの会社一筋で頑張り、ともすれば定年退職するまで働き続ける人達なのだろう。しかし、僕はその上司とのイザコザを一つのきっかけにし、人生の分岐点として捉えてしまった。それが僕の正直な感情、魂の叫びであり、悲鳴を上げる心身全てからのSOS信号だった。
はたして自分の感情に甘えた自主退職という道を選択した結果はというと、容易に想像できるのだが、都会の現実は当然のようにドロップアウトした者には厳しかった。しかし、辞表を受理された日の一日は今でも忘れられない。それは何とも言えぬ開放感で、「俺は今日から何をしたっていいんだ!俺は自由を手にしたんだ!」という喜びに打ち震えていた。
それから、特に何もやることも目的もない僕は、とりあえず生活費を稼ぐために、本気でギャンブラーになることを目指した。俗に言うパチプロというやつである。しかし、学生時代にパチスロにハマリ、根っからのギャンブル狂となっていた僕にとって、冷静さと勝逃げが鉄則のプロの世界はそんなに甘くはなかった。それはまさに僕の人生を象徴するかのように、浮き沈みの激しいものであった。
「このまま日本に居ると、俺はパチスロに全てをやられて破滅してしまうかもしれない…」
もはや夢遊病患者のように都会を彷徨い、ギャンブルに明け暮れる毎日を送っていた僕に、エビスさんからタイ行きの誘いが来たのは丁度そんな時だった。僕はパチスロの呪縛から逃げるように、ただ気分転換できるかもしれないという思いに駆られ、エビスさんの誘いに応じ、タイ行きのチケットを購入した。それは僕にとってまさしく日本からの逃避行であった。
日本の社会から脱落した人生の落伍者。世間から見ればそんなところだろう。しかして、そんな甘ちゃんの僕をタイというお国柄やパタヤの街は優しく暖かく包みこんでくれた。いや、現実には日本人の僕という一人のちっぽけな存在など、世界各国入り乱れた人々の喧騒に掻き消されるだけで、その状況そのままに、誰も僕のことになんか興味も関心もないし、放っておいてくれるということだ。後ろ指を差されることもない、知り合いから連絡がかかってくることもない、誰からも束縛されない自由空間。そんな環境に身を委ねていることがとにかく心地よかった。
「パタヤに住んで俺の仕事を手伝わないか?何か一緒にビジネスをしないか?」というリュウさんからの誘いは、僕の感情に衝撃を与え、魂を揺さぶり、一気に視界が晴れ渡るような話だった。
エビスさんと知り合い、駐在員時代の話や将来のタイ移住計画などを散々聞いていた僕は、少なからずタイ移住という淡い夢を抱くようになっていた。しかし、それは当然のように全く現実的な話ではなかった。
それが大人になりきれない子供のように会社を辞め、日本社会からドロップアウトし、逃げるように訪れたパタヤで、日本人長期滞在者の男に出会い、タイ移住という夢が叶おうとしている。
タイで何をするのかなど別に気にも留めなかった。異国で出会った素性もよく知らない男を本当に信用していいのか、といった不安感など微塵も感じなかった。
もちろん、独りだったら、こんな無茶な選択などしなかっただろう。結局、僕の人生はこれまでずっとこんな調子で、両親の期待に応えるように従い、他人に影響され、誘惑されて、甘えるように我が身を委ね、流れに身を任せるように、転がってきた半生だった。それは上流から下流へと流され続ける小粒の石ころのようなものだ。
僕は目に見えない何者かに背中を後押しされるように、タイ移住を決断した。
僕の石ころ人生は、穏やかな南国の風にフワフワと乗せられて、、、
一体自分がどこに向かっているのか、全く行方知れずのままに、、、
突如、激流に飲まれるように急降下し、深い暗闇の大渦に引きずりこまれたが、
そのうち浮き上がり、再び、勢いよく軽やかに転がり始めた。
タイ移住生活14年間の放浪物語―フィクション50%+ノンフィクション50%=(ハーフ&ハーフ)ストーリー