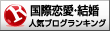「ハロー、ニック?俺、ヒロだけど…」
「オー、ヒロー?コンバンワー!ゲンキー?」
「今、日本に数日戻ってきてるんだけど。ニックに会いに横須賀に行ってもいいかな?」
「ホント?オーケー、もちろん、いつでもウェルカムだぞ!」
二度目となる失業保険の支給日に合わせて日本に帰国した僕は、友人の家に足を運んだが、子育てに忙しくしている家庭に何日もお世話になるのはやっぱり悪いなと気が引けて、到着した晩すぐにニックに連絡を取った。他にこれといった用もないので日本滞在期間は4、5日程。翌日ハローワークに出向いて給付金を手にすると、その足で横須賀に向かった。前回同様、ニックは待ってましたとばかりに暖かい歓迎ムードで出迎えてくれたが、彼の店に連れて行かれると以前とは少し様子が違うようだった。
前回訪れた時に比べて、何かスタッフたちの態度がよそよそしい。それに僕は明らかに招かざる客といった不穏な雰囲気が店内に漂っていた。それを知ってか知らずか、オーナーであるニックはお構いなしに僕をカウンター席に誘い、いつものように色々と飲み食いさせてくれたが、彼とスタッフたちの間にもギクシャクした空気が流れているように感じた。その理由は酔いが進むうちに、ニックの口から語られることになった。
「実は俺もお前らみたいにパタヤでロングステイしたくてな。今後はスタッフに店を任せて、日本とタイを行き来する生活にチェンジするつもりだって彼らに伝えたんだよ」
「えーっ、マジでー!?それでいつからタイに行く予定なの?」
「今月中にも一度行こうと今チケットを調べて計画してるところだ」
「ワオ、そりゃ、こんな険悪なムードになるはずだ…」
僕はニックもパタヤに移住してくるんだという話に嬉しくなる反面、スタッフたちから度々こちらに向けられる刺々しい視線と重苦しい空気に喜びをあらわにするわけにもいかず、まさに板挟みのような状況だった。スタッフたちからすれば僕はニックの日常を変えてしまった悪友のような存在であり、タイ行きを助長した元凶だと思われていたのかもしれない。ニックは数年ぶりに訪れたタイで僕らに出会い、それから帰国した後にタイや僕らの話ばかりしていたと聞かされていたので、当然そう思われても仕方のないことだった。そんな悪の根源のような僕が全く悪いタイミングで店を訪れてしまったのだ。
「もうこうなってしまった以上はしょうがない。俺はオーナーで彼らとは友達関係のままじゃダメなんだ。それに俺ももう若くないしな。このままずっと日本に住み続けるつもりもないし、これが丁度いい機会だったのかもしれない。まあ、俺の人生なんだから俺の好きなようにするさ」
ニックはスタッフたちとの間にできてしまった軋轢を冷めた態度でとらえ、最終的には自分の人生へと転化させるように話をまとめた。彼の中ではもう全てが決まったことですでに吹っ切れているのだろうか。ニックは僕を味方につけた悪ガキのように、スタッフたちとの間に漂うギスギスした空気を半ば面白がるようにパタヤ行きに歓喜し、レモンサワーのジョッキを突き出して乾杯を繰り返した。彼には空気を読むということがないのか、いや、それを感じたとしてもさほど気にしないということなのか。そんな彼を見てやっぱりアメリカ人なんだなと僕は思った。
その日は閉店を待たずに、スタッフたちから逃げるように店を後にした。
翌日はニックのお願いで、外国人登録関係の手続きとやらで市役所に付き添うことになった。開店当初は色々と世話を焼いていてくれていたスタッフたちも、最近では面倒くさがってあまり付き合ってくれなくなったようだ。役所の係員は中高年ばかりで全くといっていいほど英語が通じないんだとニックが愚痴をこぼす。窓口に呼ばれると、僕はニックの横に付き添い、彼の言葉をおぼろげながら理解しては通訳するように係員に説明した。
「今日はヒロがいてくれて助かったよ。いつも俺が行くと係員たちがアタフタしだして時間がかかって大変なんだが今日は早く済んで良かったよ」とニックは喜び、僕はいつも奢ってもらってばかりの彼の役に立てたようで嬉しかった。
その後はお礼にとニック行きつけのファミリーレストランに連れて行かれた。ここは英語のメニュー表記があるから重宝してるんだと言い、ニックはお気に入りのカツ丼セットを注文した。日本人ばかりの客層の中で大柄の外国人であるニックは目立つ存在なのだろう、周囲の人々がチラチラとこちらの様子を窺うような視線を向けてくる。料理が運ばれてくるとニックの前には箸と別にスプーンとフォークが用意されたが、ニックは少しぎこちない箸使いでカツ丼を口にかきこんでいた。
食後のコーヒーを飲みながら二人まったりしていると、店外の街並みをぼんやり眺めていたニックが感慨にふけるように口を開く。
「ヒロ、日本の街中を見てごらんよ。店の看板にしろ、レストランのメニューにしろ、とにかく英語表記が少ないんだ。アパートを借りたり、携帯電話を持つにも、全て契約のための紙が必要で、日本は何かと面倒くさいんだよ。社会全体が契約で縛られているようだ。我々外国人には全く住みづらい国なんだよ。それに比べてタイはどこでも英語が通じるし、英語が至る所に溢れている。携帯を持つのも、住まいを借りるにしても大そうな契約書なんて必要ない、パスポートだけあればOKだ。だから移住するのも簡単なんだよ」
「うん、確かに言われてみればそうかもしれないね」
それは外国人のニックが日本に数年間住んで痛感した違和感であり、彼にとっては異国である日本の現実であった。とはいえ、うんざりするように語る嘆き節も彼の中では過去のものであり、想いはすでにタイへと向けられているようだった。結局、僕は日本帰国中ニックのマンションに二日間お世話になったが、彼の店には二度と顔を出すことはなかった。
「Hey Guys, I'm Coming Pattaya!」
タイに舞い戻り、ほどなくしてニックは本当にパタヤにやってきた。居ても立ってもいられなかったのか、僕に話していた予定より随分早いようだった。ニックは日本から予約していたホテルに数日泊まっていたが、空きがあることを知ると、すぐにリュウさんがいるホリデイホテルへと引っ越してきた。リュウさんに色々と手配してもらい、彼もマンスリー契約で滞在することにしたようだ。しばらくはパタヤに住んで、2~3ヶ月に一度ぐらいのペースで日本に戻る予定らしい。
日本で借りているマンションはどうしたのか訊くと、すでに数ヶ月分の家賃を前払いしているようだ。そのうち誰かに安く又貸しするか、パタヤに長くいるようなら解約して、物置がわりに安いアパートでも借りるつもりだという。日本に戻るときは好きに使っていいぞと僕に言ってくれたが、ニックのいない横須賀までわざわざ足を延ばすことはないだろうと思い断った。それにあと一回で失業保険の支給も終わる。そしたらもう日本へは当分戻ることはないだろう。
それから、ニックとリュウさんと僕の三人でつるむようにパタヤの盛り場へと繰り出す日々が再開した。
それまで足繁く通っていたソイブアカオのクッキーバーにはあまり足を向けなくなっていた。説教じみた会話から言い争いのような気まずい関係になってしまったおじさんと二度と顔を合わせたくないという思いもあり、日本人長期滞在者が集う早い時間帯は避けるようになり、いつしか深夜の締めに立ち寄る店へと変わった。ニックがパタヤに住み始めて暫くしてから、クッキーバーに取って代わるように僕らの集合場所になったのが、ソイパタヤランドにあるニック行きつけのバービアだった。
ソイパタヤランドはパタヤ最大の歓楽街ウォーキングストリートから歩いてすぐの近距離にあり、数軒のゴーゴーバーやバービアが点在するソイ(小通り)である。中でもセカンドロードに面した入口から顔を覗かせるボーイズタウンが有名で、世界各国の男好きたちが集う通りでもあった。一歩足を踏み入れればゴーゴーバーならぬゴーゴーボーイが密集するゲイタウンだ。そんな通りの一角にニックが慕うジョージの店はあった。ジョージもニックと同じアメリカ人で退役軍人らしい。
歴史を感じさせる古びた店ではジョージの奥さんである物腰の柔らかい眼鏡をかけたタイ人おばさんがキャッシャーをしている。在住歴20年以上と長年パタヤでバー経営をしながらリタイア生活を送ってきたジョージは、ニックにとって米軍の先輩であり、移住のお手本にしている生き字引のような存在だった。パタヤの黎明期から隆盛時代を知るジョージを頼って、店には多くの欧米人が集っていた。これから何か商売をしようと企んでいるリュウさんと僕にとっても、彼らから聞くパタヤの昔話や現地情報はとても参考になるものばかりだった。
それから本格的にパタヤ移住を始めたニックは、知り合った時のように毎晩あちこちのバーをはしごして散財する飲み方は止めて、ジョージに影響されるように落ち着いた暮らしに方向転換したようだった。毎朝早く起きて、ビーチロードまで散歩がてらウォーキングするのが日課らしい。それから海の見えるカフェに入り、モーニングコーヒー付きの朝食を取りながらパタヤの地元新聞に一通り目を通す。昼間は海でのんびりするか、ジョージの店で借りたレンタルバイクで街を探索する。ニックは自分の資産を運用して、何かパタヤでビジネスを始めるか、あるいは不動産投資することに興味を持っているようだった。
ニックは毎晩のようにジョージの店にたむろし、しっぽりと呑むことが多くなった。そして暇を持て余すと「お前ら何やってるんだ?ジョージのバーにいるから飲みに来いよ」と僕らに誘いの電話をかけてくる。だから僕らもジョージの店でのんびり過ごすことが多くなった。それはエルという恋人がいる僕にとっては好都合でもあった。ニックはリュウさんと僕、それにエルがいたとしても全く問題ないように、いつも全ての会計を支払い奢ってくれた。すぐに彼は僕らのボスのような存在になっていった。
ニックが経営する横須賀の店が閉店となる夜10時(日本時間の深夜0時)頃、日本にいるスタッフからニックの携帯に国際電話がかかってくる。パタヤに来てからは、毎晩その日の売り上げを報告するように義務づけているらしい。ニックはスタッフたちとの馴れ合いの関係に終止符を打ち、オーナーとしての自由なポジションをすでに確立させたようだった。
「ホント?スゴーイネ!アリガトゴゼェマシター」
ものの数分の会話だが、ニックが電話口で話す片言の日本語はいつもこんな調子だった。「お前ら聞いてくれよ、今日の売り上げは**万円だったらしい」。スタッフたちの心配をよそにニックが日本を離れてからも、何ら変わりなく店の売り上げは好調をキープしている様子だった。もちろんそうなるためにオーナーとしての粋な計らいもあったようだ。ニックはオーナーとはいえ自分の我がままを通してタイ移住を強行すれば、彼らの反感を買い、いずれ経営の士気が下がることを懸念していた。だから其々のスタッフには新たな役職を与え、それなりに給料UPを交換条件としてきたようだ。
また、ニックには毎月30万円程の給料が支払われるようになっているらしい。もちろん売り上げから諸々の経費を差し引いた余剰資金は会社の資金としてプールされていく。それに米軍からも毎月数十万円が年金として振り込まれる。それらの資金はタイで暮らしていくのに十分すぎるほどだった。
「俺は大酒飲みだし、ヘビースモーカーだから、多分そんなに長生きは出来ないだろう。大好きな日本に数年住んで、スタッフたちにも恵まれたおかげで店も順調だ。俺には十分すぎるほど金も稼いだし、これでもう大満足だよ。だから今後はタイをメインにして、のんびり老後をこっちで暮らしていくつもりだ。彼らのことは信用している。もし俺がいない間に会計をごまかして横領されるようなことがあっても、それは多少のことなら致し方ないことだと思ってるよ。それにゆくゆくは彼らに店を譲ろうとも思ってるんだ…」
ニックのスタッフたちに対する感謝の気持ちや寛容な姿勢に、僕はなんて優しくて男気に満ちたデッカイ男なんだと深く感動するばかりであった。そして、そんな根っからのボスのようなニックの寛大な性格は僕らに対しても同様に向けられることになった。
お前らは何をやるつもりなんだ?こういう商売をやってみたらどうだ?この前どこそこのバーで不法就労していた欧米人がポリスに連行されて罰金をくらったらしいぞ。ニックはジョージの店や欧米系の長期滞在者たちから知り得た様々な現地情報を逐一僕らに語り、教えてくれた。
「お前ら、ウォーキングストリートにある○○ってアイスクリームショップを知ってるか?実に面白い話なんだよ。あの店のオーナーはイタリア人なんだけど、元々は30歳ぐらいの時にバックパッカーみたいな貧乏旅行してた奴がパタヤに流れ着いたんだ。丸々太った人の良さそうな感じの兄ちゃんだ。そいつはとにかくイタリアでいうジェラートが大好物だったんだが、暑苦しいパタヤでアイスを食べたいのに、店が全く見当たらないことに愕然としたんだ。それで思い余って自ら作ることにしたってわけさ。それが大当たりして今ではタイ各地にチェーン展開してるって話だ。パタヤが始まりだぞ。夢のある話だろ?」
そんな感じでニックはいつも僕らを焚きつけるように色々な話をしてくれた。アメリカンドリームならぬパタヤドリームだ。僕らはニックの話に影響されるように、自分たちで出来る何かを探し求めて日々パタヤの街を徘徊し続けた。
時を同じくして、日系アメリカ人のデニーさんがパタヤを訪れた。僕がパタヤ移住を決めた頃、金欠だったことから、資産家である彼をリュウさんから紹介してもらい、お金を借りていたのだ。それは2万バーツ程だったが、パタヤで質素な倹約生活を送っていた僕にとってはすでに大金へと変貌していた。それでも出会ったばかりで見ず知らずの僕に、無保証、無利子で快く貸してくれたのだ。デニーさんに会うことになると、僕は心許ない資金の中から2万バーツを用意し、彼にお礼を告げて返済しようとした。しかし、デニーさんはそれを受け取ろうとしなかった。
「ヒロ君はきちんとした人ですネ。でも、ボクは返してもらおうなんて思ってなかったヨ。君がリュウさんの友達で困っていたようだったから、ボクはあげたつもり。アメリカだったら返してくれる人なんていないヨ。だからボクは嫌いな人には貸さない。友達からお金を貸してくれと言われたら、いつでもあげるつもりだけ。ダイジョウブ、ボクにとっては大した金額じゃないから。さあ、どこかに飲みにイキマショウ!」
片言の日本語で話すデニーさんに「いや、さすがにそれは悪いですよ…」と僕は意固地になって返そうとしたが、デニーさんは僕を気遣ってか決して受け取ろうとしなかった。困ったようにリュウさんに目を向けると、リュウさんは黙って頷きながらウインクするだけだった。そんなリュウさんを見て、僕はリュウさんは初めからこうなることが分かっていたのかと思った。それから僕はデニーさんに頭が上がらない、言うならば舎弟のような存在になった。
投資家であるデニーさんも、いずれパタヤに移住することを目論んでいる様子で、話の内容はいつもパタヤのコンドミニアムや中古ホテル物件といった不動産投資の話ばかりだった。それに彼は弁護士の資格を持っているらしく、タイでの会社設立に関する法律を色々と調べているようだった。無知な僕は彼が語る壮大な話にチンプンカンプンだったが、興味津々のリュウさんはデニーさんの話に熱心に耳を傾けていた。
リュウさんを仲介して、デニーさんとニックも知り合うことになった。エリート階級の富裕層な投資家といった雰囲気のデニーさんに、成り上がりのアウトローな商売人といった感じのニック。対照的な二人のアメリカ人に囲まれて、それまで僕に根付いていた日本人的な価値観はひどく揺さぶられることになった。
リュウさんはデニーさんが言うところの「頭を使い資金を運用して賢く立ち回って労せず金を生む方法」に甚く感化されているようだった。
一方、資金も経験もない無い無い尽くしの僕はニックが語る「人を第一に知恵を振り絞り身体を精一杯フル稼働させて成り上がっていく」アメリカンドリーム的な思考に心を鷲づかみされていた。
手段は違えど、二人のアメリカ人が口にするシンプルな合言葉。
「MAKE MONEY(メイクマニー)」
タイで生きていくために、生き残っていくために、僕はこのメイクマニーという言葉だけを頼りに、何だっていい、とにかくやるしかない、やっていくしかないんだという決意に打ち震えていた。
タイ移住生活14年間の放浪物語―フィクション50%+ノンフィクション50%=(ハーフ&ハーフ)ストーリー