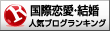「ねぇ、ティーラック(ダーリン)、今日はあなたを連れて行きたい場所があるの。だから夜は空けておいてね」
「何、どうしたの急に?どこに行くつもりなの?」
「ううん、まだ教えない。私の大好きな店よ。今日は私が奢るから心配しないでね…」
いつもカラカラと笑っている明るい性格のエルが、ある日、いつになくかしこまった態度で僕を誘ってきた。意味ありげなもの言いにふと嫌な予感が頭をよぎったが、彼女の友達ドゥアンも一緒に行く予定だというので、何か食事会でもするのかなと思いを巡らせた。僕の友達も誘っていいからと言うので僕はリュウさんに声をかけた。
まだ夕陽が沈む前の明るい時間に、僕らはリュウさんを迎えに彼の住まいへと足を向けた。ドゥアンは後から合流するようだ。「何、何、どこに行くのさ?」、落ち合って早々せっかちなリュウさんは怪訝な顔つきをエルに向けてタイ語でまくし立てたが、「今日は私が奢るから黙ってて!」と、エルは着いてからのお楽しみとでも言うようにリュウさんを制した。
歩いて通りまで出ると、すぐにエルは乗り合いタクシーのソンテウを自ら捕まえた。助手席の窓から顔を突っ込み、何やら運転手と交渉している様子。どうやら車を貸切って目的地へと向かうようだ。交渉を終えたエルがガイドのように僕らを手招きして呼び寄せる。「早く乗って!」と彼女に催促され、僕とリュウさんはそそくさとピックアップトラックの荷台を改造した後方座席に乗り込んだ。
「もしかして今日ってエルの誕生日?」、「いえ違いますよ」、「じゃあ誰か友達の誕生日パーティーか何かかなぁ」、まだ詮索を止めないリュウさんと僕のやり取りに、エルは素知らぬ顔をして微笑むばかりだ。「友達のドゥアンも来るみたいだし、どこかお気に入りの飲み屋かレストランにでも行くんじゃないですかね?」と僕はあやふやに回答して話を終わらせた。我々が乗ったソンテウは、やがて大通りのセカンドロードに出るとパタヤを北上し始めた。
しばらく走り、車は北パタヤのショッピングモールBigCを通過しても尚、直進を続けた。それからイルカのモニュメントがあるロータリーを右折し、ナクルアと呼ばれるパタヤ北部エリアへと進入した。通りの両サイドに点々と軒を連ねる廃れた雰囲気のバービア群に目を向ける。ローシーズンのせいか場末を感じさせる通りは人々の往来もまばらである。車はまだ止まる気配を見せない。エルはただ黙って南国の穏やかな夜風を浴びるように車外の景色を眺めているだけだ。そのうち目に飛び込んでくる風景は、観光客の姿すら見かけない、ホテルや商業施設などが全く見当たらない現地人エリアの様相に変化した。
いったいどこまで行くのかと不思議に感じ始めた頃、ようやく車が右折して小さな通りに入った。「ははーん、多分あそこじゃないかなー?」とリュウさんは予想がついたように口を開き、何やら僕の知らないタイ語でエルに訊ねた。その会話の内容を理解できない僕は二人のやり取りに耳を傾けるばかりだ。エルが少し驚いた表情で「チャイ、チャイ(そう、そう)」と答える単語で、どうやらリュウさんは行ったことがある場所なのかと分かった。そうこうしている内に、民家ばかりの路地を突き進んだソンテウはようやく停車した。
車を降りると、簡素なタイ語の看板がかかった店らしき入口へと促される。「これは何屋さんなんですか?タイ料理のレストランか何かですか?」とリュウさんに訊ねると、「ここは釣り堀があるレストランだよ。俺も前に一回来たことがあるから」と店の正体を教えてくれた。鮮やかな色合いの花柄シャツを着たスタッフの女性が、「サワディーカー」とワイ(合掌)しながら我々を出迎える。店内に足を踏み入れると、すぐに魚市場のような生臭い匂いが鼻をついた。ガヤガヤと店員たちが屯する厨房らしきスペースに目を向けると、傍らに大型の水槽のような生け簀が置いてある。中を覗き込むと特大サイズの鯉とかブラックバス、ナマズみたいな淡水魚が窮屈そうに泳いでいた。
スタッフに案内されて再び屋外へ出ると、目の前に沼池とかダムを思わせる広大な貯水池が姿を現した。その池の周りを囲むように、ログハウス風の木作りの小屋がぽつぽつと建ち並んでいる。早い時間帯のせいか、まだ客の姿は見当たらず僕らは一番乗りのようだった。すぐにエルは彼女のお気に入りらしき敷地中央に佇む小屋を選んだ。小屋の内部はこじんまりとした6畳ほどのスペースで、竹製のテーブルセット、安っぽいソファーなどと共にカラオケマシンが設置されている。タイ料理をつまみに酒盛りしながらカラオケに興じる。それはカラオケ好きのエルにうってつけの店のようだった。
池を臨む小屋の前にはウッドデッキが敷き詰められており、軒先から釣りを楽しめる。魚が釣れればそれをお好みのリクエストで調理してくれるようだ。手際よくエルがドリンクと数品のタイ料理を注文すると、すぐにスタッフが人数分の釣り道具セットを持ってきてくれた。使い古したリール付きの釣竿で、仕掛けはルアーではなく餌釣りらしい。小汚いバケツの中に細かく千切られた大量の食パンが入っており、これを練り餌として使うようだ。僕は少年時代に食パンを丸めて川釣りに興じていた時の自分をふと思い出した。フナや鯉釣りに出かける際、本来ならば餌用のゴカイとか練り餌の材料となる専用の粉を釣具店で購入するのだが、そのお金がなくて、近所の田んぼでミミズを捕まえたり、台所にある食パンをくすねて餌代わりにしていたのだ。
釣り糸には大きめのウキ、その下に螺旋状の針金と釣り針が付いている、吸い込み仕掛けといった感じだ。その螺旋の針金部分と釣り針に、食パン片を丸めた団子状の練り餌を装着する。もう何年ぶりになるだろうか、久しぶりの釣りに嬉々として興奮した僕は、昔の記憶を掘り起こすように釣竿を振り、糸を垂らしてリールを巻いた。気づくと辺りはオレンジ色の夕陽に染まり、水面に降り注いだ穏やかな光がキラキラと宝石を散りばめたようにそこかしこで揺れていた。
およそ30分が経過しても、僕らは誰一人として魚を釣り上げることが出来なかった。リュウさんはすでに飽きた様子で、仕掛けをキャストしたまま釣竿を地面に放置して、煙草を燻らせている。釣りは忍耐を求められる。水中にいる魚との騙しあい、根比べである。それにここは釣り堀だ。魚がいないはずはない。僕は何度となくリールを巻いては練り餌を付け替え、大きな団子状の仕掛けを遠くへ、遠くへと投げ続けた。釣りにはあまり興味がないのか、エルも数回投げただけで止めてしまった。彼女は僕の傍らに佇み、何とか一匹釣り上げようと夢中になっている僕を応援するように見守るだけだった。
そのうち夕陽が沈み、辺りは敷地を囲む小屋の電飾に包まれたほんのり暗がりの空間になった。注文したタイ料理が続々と運ばれてきたところで、僕らは釣り遊びを一旦休止して小屋に入ることにした。この店の名物なのか、テーブルには定番のタイ料理の他に数種類のナマズ料理が並んでいる。エルが皿に取り分けながら「キン・ダイ・マイ?(食べられる?)」と僕に訊ねる。初めてのナマズ料理に僕が幾らか敬遠する仕草を見せると、エルはそれをフォークとスプーンで器用に装い、僕の口元に運んだ。
それは「ヤム・プラードゥック・フー」という名前のタイ料理で、ナマズのことをタイ語で「プラードゥック」というらしい。細かくほぐしたナマズの身をサクサクに揚げて、カシューナッツや玉ねぎ、青マンゴー等と一緒に和えた料理で、甘辛酸っぱいタレを掛けて食べる。微妙に感じる生臭さがどうにも気になって僕の口には合わなかったが、リュウさんは「これは精がつくから身体にもいいんだよー」とタイ人みたいにバクバク食べていた。
酒が進んで酔いも良い加減になると、いよいよカラオケタイムが始まった。エルはこの時間を待ってましたとばかりにマイクを握り、定番のタイ歌謡曲に美声を響かせた。そのうちエルの友達ドゥアンも合流し、僕らはタイ料理をつまみに酒盛りしながらカラオケの宴に興じた。
小一時間ほど過ぎた頃だろうか、腹も満たされ、さてもう一度、釣りでもするかと小屋の外に出ると、リュウさんの釣竿が失くなっているのに気づいた。僕とエルの釣竿は軒先に立てかけられている。そういえばリュウさんは仕掛けを投げて、そのまま放置していたはずだ。水面に目を向けるとウキの姿も見当たらない。しげしげ眺めていると、岸から数メートル先にリュウさんの釣竿が落ちて流されているのが視界に入った。
「あれっ!これってまさか?リュウさーん!!多分、リュウさんの釣竿に何か掛かってますよー!!」
「えーっ!!まじでーーっ!?」
僕の驚く声に皆が一斉に小屋から飛び出してきた。水面に浮かんだリュウさんの釣竿はどんどん岸から離れて流されている。僕とリュウさんは残った釣竿でそれを手繰ろうとしたが、すでにもう竿が届かない距離まで流されている。かかった魚がそれを振りほどこうと暴れ、水中深くまで引きずり込んでいるのだ。ヤバイ、これは失くしてしまったら弁償ものだ。僕らは餌もつけずに仕掛けを投げて、流されていく釣竿を釣り針で引っ掛けて、何とか回収しようと奮闘した。
ほどなくして、投げた釣り針が水中を漂うライン(釣り糸)に絡まるようにして引っかかった。ようやく釣竿を引き上げて、リールを巻くと、ゆうに50cm以上はある特大サイズのナマズが釣り上がった。皆揃ってその珍騒動に笑い転げ、歓声を上げた。結局、僕らが釣り上げた魚はその一匹だけだった。そのナマズは数十分後には僕らの酒盛りのつまみとなった。
釣り遊びに飽きた僕らは再び小屋に戻り、誰が言い出したのか、一気飲みゲームを始めて互いのグラスをつき合わせた。それはジャンケンのように「ヌーン、ソーン、サーム(1、2、3)」と掛声をかけながら皆一斉にグー、チョキ、パーを出して、仲間外れの一人が罰ゲームで一気飲みするだけという単純なゲームだ。お酒に弱いエルを気遣って、僕は彼女の分まで飲むことになった。
そのうち僕らは上機嫌に酔っ払い、やがて一気飲みゲームは採点式のカラオケマシンを利用した遊びへと趣向を変えた。僕は、エルとドゥアンによるカラオケメドレーに耳を傾け、リュウさんが歌うタイソングの曲調を覚えるように口ずさんだ。それから同じ曲を入れて練習がてら僕もタイ語のカラオケに挑戦してみたが、いい加減な発音が面白可笑しく聞こえるのか、二人のタイ人女性に爆笑されるのがオチだった。
もう何時間、釣りにカラオケにと飲み騒いだだろうか。すっかり夜も更け、心地よい泥酔感に浸っていると、ドゥアンがエルに何やら耳打ちしている姿が目に入った。もうそろそろ宴もお開きの時間なのだろうか。その様子をご機嫌に酩酊しながら眺めていると、エルが僕の傍に近寄り手を取って、小屋の外へと連れ出した。散々飲み食いしたので支払いが心配なのだろうか。心なしかエルは神妙な面持ちを漂わせて僕に告げた。
「ティーラック(ダーリン)、ちょっといい?」
「何、どうしたの?お金なら僕も出すから心配しないで」
「ううん、違うの。ちょっと話がしたいの…」
そう言うと、エルは僕の手を引きながら小屋を離れて歩き出した。うっすら暗闇の空間、周囲にひと気のない場所まで僕を連れて行くと、誰もいない小屋を選び、軒先の木製ベンチに座ろうと僕を促した。
「何、何、どうしたの?」
そう言いながらも、僕は不安な思いに駆られて、急激に酔いが醒めていくのを感じた。エルは何か口に出そうと、決意を固めたような表情をしているが、ただ黙って目の前に漂う漆黒の水面(みなも)を眺めるばかりだ。敷地の向こうから宴会で盛り上がっているタイ人客たちのざわめきや歌声が夜風に運ばれて聞こえてくる。
やがて、彼女は決心したように口を開いた。
「ここは私がパタヤで一番大好きな場所で、一度あなたを連れて来たかったの…」
「うん、ありがとう。今日はとても楽しかったよ」
「ねぇ、ティーラック(ダーリン)、私はあなたのことを愛してる。でも、ソーリー…」
僕にそう告げると、エルの大きな瞳から零れるように大粒の涙が溢れ出した。
僕は何となく事情を察し、「マイペンライ(大丈夫)…」と彼女の頬に手をやり、その涙を拭ってあげた。しかし、それ以外の言葉は見つからない。ただ、マイペンライを繰り返すことしか僕にはできない。
そして、ひとしきり涙を流した後、エルはくしゃくしゃに歪ませた顔を僕に向けて恨めしそうに告げた。
「もう、あなたも分かってると思うけど。私には子供がいるの。カスタマーの彼との間にできた子供なの…」
やっぱり彼女は僕に嘘をついていたのだ。欧米人の彼とは肉体関係がないなどという話は、嫉妬する僕を慰めるための偽りの言い訳に過ぎなかったのだ。日に日に大きくなっていく彼女のお腹が、もう嘘を隠し切れないところまで来たということなのだろう。僕が感じていた前兆、そして違和感がリアルな現実となってとうとう姿を現した。衝撃の事実に僕は愕然と肩を落とすだけだった。
彼女にかける言葉は見当たらない。切なそうに彼女が言葉を紡ぐ。
「妊娠が分かったのは、あなたと出逢う少し前のことだった…。もう少し早くあなたに出逢えていれば…」
「私はどうすればいいか分からない…」
彼女は目に涙を浮かべて思いを吐き出した。
「ドゥアンからは欧米人の彼と結婚するように勧められているけど、もしあなたが望むなら、私は彼と別れてもいいと思ってる。でも、お腹の中の子供は産むつもり。彼との子供だけど、私が天から授かった私の子供だから…」
様々な思いや感情が一度に脳内を駆け巡り、魂を刺激し、僕は訳が分からなくなる。たちまち抑えきれない衝動の波が心の奥底から湧き出るように溢れ出す。それは涙となって姿を現した。僕は必死にそれを隠そうと目を拭いながらエルに告げた。
「マイペンライ、、、ポム・ラック・クン(僕は君を愛してる)」
ウワァーとわめくような泣声をあげて、エルは僕の胸に飛び込んできた。僕は彼女の華奢な身体を受け止め、覆うように背中に手をまわして、きつく彼女を抱きしめた。エルは僕の胸に顔を埋めて号泣した。僕は彼女の頭を頬ずりするように嗚咽を洩らした。そして、僕らはただ目の前にある欲情を貪るように互いの唇を奪いあった。
二人の行く末がどこへ向かっているのか、僕にはもう知る由もなかった。
タイ移住生活14年間の放浪物語―フィクション50%+ノンフィクション50%=(ハーフ&ハーフ)ストーリー