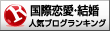『それは、日本に「腐凶(フキョウ)」という名の時代があった頃のお話です・・・。得怒(エド)の町は、呼んで字のごとく盗人や人斬りといった豪族たちで溢れ、まさに腐敗した悪の巣窟のようでありました。人々は日々、不安と恐怖に苛まれる毎日。でも、それに対抗する強靱な精神力も、狂人じみた考えも人々には、到底ありません。彼らは、ただ、何となく生かされるようにいつ果てるか分からない霧の中を、悶々と暮らしているのでありました。【又助(マタスケ)】とは、そんな時代に生きた偉人のような異人です。彼の本名は【吉原 又助べえ衛門】と言い、色街としてその名を馳せる「吉原(ヨシワラ)」の創設者だという説も(多少)残っているほどです。また、「助べえ」という言葉の由来も彼からなのでは?という有力筋からの風の便りも届いてきそうな心地よい初夏の季節~到来・・。
すると、また、又助のマタがウズウズと騒ぎ始めるのでありました。それは、いつもの発作のようなもので、性乱(戦乱)が近くなったことを意味します。そして、それこそが、彼が侍である何よりの証拠でもあるのです。ただ、その時代に「侍(サムライ)」という身分があったわけではありません。その当時の「侍」とは、人々の生活スタイルとか暮らし向きといったカテゴリーの一つでありました。そして、だいたいの人々にとっては、腐凶(フキョウ)の時世をサラリ生き抜く「鎖裸利胃万(サラリイマン)」という生き方が主流だったわけであります。
「侍」というスタイルは、その当時としては、何とも時代遅れでした。人々は、「奇業(キギョウ)」と呼ばれる寄り合いのような組織に属し、毎日、「死誤吐(シゴト)」に精を出しています。まさに、精魂尽き果てるまで、延々と続く作業。ただ、それが「奇業」というシステムですから、誰も文句は言いません。しかし、「侍」である又助には、そのような生き方は到底出来ません。何人からも束縛されることを拒む。それが「侍」というものなのです・・・。

しかし、「侍」というスタイルを貫くだけで、当時のご時世を生き抜くのは非常に困難なことでした。この時代にも、「金玉子(キンタマゴ)」と呼ばれる現在でいう貨幣のようなものが流通していたからです。そして、ほとんどの人々は、その「金玉子」を収集することにだけ、生きがいを感じていたのでした・・・。「金玉子」とは、幻の不死鳥と呼ばれる「ガチョーン」の卵から出来ており、その何とも言えぬ神々しい黄金色に人々は魅了され、そして、「金玉子」を多く持っていればいるほど子宝に恵まれ、子孫まで一族は繁栄するという定説もあったぐらいですから、それは仕方のないことかもしれません。だから、又助は、至極たまに、用心棒などの頼まれ事(今で言うアルバイト)を引き受けることにしていました。ただ、それも、彼の気が向いた時だけのことで、だいたいは、ふらり糸の千切れたタコのように、風任せ~身を任せ~気の向くまま、あちらこちらへと風来坊なスタイルを貫き通し続けるのでありました。
しかし、そんな性格が天を味方につけることもあるようです。又助は、博打遊びに興じることが三度の飯よりも大好物でしたが、「馬事(ウマゴト)」や「魔雀(マジャン)」でひと稼ぎすることもよくあることで、そうなると、だいたいその日の晩は、色事をしに「姉音街(ネェオンガイ)」へと繰り出して~散財というのがパターンでありました。でも、それが「侍」というものであり、それが粋ってなもんよ!とばかりに、又助は
また一口、愛飲する「象美亜(チャンビア)」を勢いよくグビリ飲み果てるのでありました。その時代には、いろんなスタイルの「侍」たちが存在していました。ケンカ自慢の「傾奇者(カブキモノ)」、音楽好きの「六九出者(ロクデモノ)」、そんな中、又助は「呂里悪(ロリオ)」というカテゴリーの「侍」でありました。というのも、彼は、天性の好色男。とにかく、博打で一山当てれば、亜細亜という異国の地まで、わざわざ色事をしに出かけていくものですから、それは、ごく自然な流れの通り名でもありました。
また、又助は、さすが置屋界の先駆者だけあって、亜細亜諸国の色事情というものに非常に性通(精通)しておりました。彼が頻繁に遠出する異国の地は、「部斗南無(ベトニャム)」と「中獄(チューゴク)」。ただ、当時の日本はさることながら、異国の地で異国人が平然と大手を振って街を歩けるはずがありません。だから、亜細亜に出向く又助にとって、それは戦乱であり性乱ということにもなったということです。そして、又助の色事への情熱といえば、これが性涯(生涯)通じて全く尽き果てることがなかったというから又、不思議であります。彼は「呂里侍(ロリザムライ)」というスタイルを貫き通しました。「侍」だけにこだわりは人一倍、いや100倍強もありました。とにかく、色事人性へ対する信念、哲学、いや美学というものは、全く持ってウマ並み級程ありました。
もちろん、お相手の絶対条件は、先ず、もぎたて果実でなければなりませんでした。そして、「生中信仰(ナマナカシンコウ)」に始まり、「悩混同無(ノウコンドウム)」、「生婦餌裸(ナマフエラ)」、もちろん「格安価掻(カクヤスカカク)」と、エドきっての色欲侍、色事情の求道者とまで謳われた又助の、性の煩悩が尽き果てることは一度たりともなかったという逸話まで残っているほどです。又助は、己の人性の全てを、果てることに捧げました―。そして、彼は生きる伝説 【性人】となった・・・』というのが、おおよその話の流れです。
それから、世界各地でも様々な文明が栄えては滅び~今の時代に至ったというわけですが、「日本にもそんな時代があったのじゃよ~」と田舎の長老たちによって語り継がれるような雰囲気の寓話(妄想劇)でありました・・ホロ苦)。ただ、寓話が生まれるのには、参考対象、いわゆるモデルが実在するということも確かな事実ではあります。
うっそうとした亜細亜の喧騒に紛れ、ひっそり月見草のようにたたずむ置屋のネオン街をフラリふらつく男を見かけたとき、、それが、現代に今も残る又助の末裔・・・。「呂里侍(ロリザムライ)」なのかもしれません。( 辛口ドライ!)
辛口ドライ!)