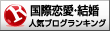いよいよタイ移住へ向けた出立の日が間近に迫っていた。
東京にいる友人知人で僕がタイ行きを伝えていたのは、私物を処分する際に事実を知られることになったバーテンのジョーさん、それと幾ばくかの荷物を預かってもらっている同郷の友人だけだった。彼とは福岡の中学時代からの幼馴染と言ってもいいような長い付き合いで、上京後の学生時代にテレビ局でのバイト、そしてテレビ関係の仕事と共に時を過ごした、僕が唯一心を許せる友人でもあった。今後日本に帰国する際は彼の住まいにお邪魔させてもらえることになった。
年末帰国した際にタイ移住を告白して以来、両親からは一度も連絡がくることはなかった。上京して8年近く、ほとんど実家には帰郷することはなかったし、電話するのも1~2ヶ月に一度ぐらいの頻度だったので、田舎の両親からすれば僕が東京にいようがタイにいようが別に違いはないように思われたが、それでも本当に親子の縁を切られてしまったような切ない感情にとらわれた。僕は実家にいる弟に最後の連絡を取り、「今後何か大事があった際はホットメールに連絡してくれ」とだけ告げた。
アパートの解約日となる出発日の数日前、不動産会社の管理人が部屋をチェックしに僕の部屋を訪れた。事情を何も知らないそのおっさんは、僕が実家の都合で仕事を辞めて田舎に帰ると勘違いしてくれている様子で、「せっかくこれまでテレビ局で数年働いてきたのにもったいないねぇ、でも福岡でも頑張ってね」と同情的な態度で励ましの言葉をくれた。すっかり家具一切が処分され、がらんとした室内に招き入れると、管理人のおっさんはこじんまりとしたキッチンの流し台や浴室トイレなど、部屋中を隈なく点検していく。そして室内の壁を見てあからさまに顔を曇らせた。
8畳程しかない室内の壁には映画のポスターやポストカードなどをベタベタと貼っていたので、それらを剥がすと粘着テープの後が至る所に残っていた。それに加えて年がら年中、室内でタバコをパカパカと吸っていたので、数年分の溜まったヤニで薄茶色に変色した壁が余計に際立って見えた。「まあ、8年もの長期間だから仕方がないけど、これだけ汚れているとさすがに壁を全部貼り替えないといけないなぁ…」と管理人のおっさんはぼやくように僕に告げた。
入居する際に敷金、礼金をいずれも二か月分払っていた。家賃は8万円だったから各々16万円である。礼金は大家と不動産会社の契約手数料のようなものだから、敷金の16万円は幾らか返ってくるのではないかと淡い期待を抱いていた。しかし、壁の劣化状況を見て機嫌を損ねたおっさんは、「これだとリフォーム代に数十万かかるから、敷金を返却するどころか、追加で幾らか払ってもらわないと割が合わないなぁ…」と不満を洩らし始めた。
「えっ、そうなんですか!?それだけはちょっと勘弁してもらいたいんですが…」
結局、僕は長年住み続けた上客で家賃の支払い延滞など一度もなかったことから、追加出費は免れることになったが、それも何がどこまで真実なのかは分からなかった。それは敷金を返したくないための口実だったのかもしれない。いずれにせよ敷金が幾らかでも返ってくればと期待していた僕はがっくり肩を落とすことになった。電気、水道代はすでに解約手続きを済ませていたので、残り数日間で発生した分は不動産会社が処理してくれることになった。最後に部屋を出て行く際にポストに鍵を投函して行くということで話は終了した。
海外旅行前の準備といえば、衣類の着替えに洗面用具に薬類など、あれこれ心配が先立ち持参する物に気を配ることになるのだが、一切の私物を処分するように整理したことで、特に思い悩むことはなかった。それに今まで何度となくタイに足を運んでいたせいか、長期滞在者リュウさんの生活の一部を垣間見ていたおかげか、大よそながらタイでの暮らしは想像することが出来た。何か必要なものがあれば、それは全て現地で調達すればいいのだ。僕がタイに持って行った物はまさに必要最低限といった感じの軽装であった。
スーツケースに不便さを感じ毛嫌いしていた僕が旅のお供として常に愛用していたのが大型のバックパックだった。それはロウアルパイン(Lowe alpine)という登山用メーカー製品で何より丈夫で機能的であることが重要だった。バックパックだと背中に背負って両手が自由になるし、階段でも悪路でも関係なく歩けるのがよかった。それにポーター(PORTER/吉田カバン)のショルダータイプのボストンバッグを持っていくことになった。
衣類は当然夏物ばかりでTシャツに下着のボクサーパンツ、靴下を各10枚ほど。ズボンは履き古したジーンズにチノパン、半パンなどを数着。それにスニーカーが数足という程度だった。日本を行き来する際はこれにアウトドアメーカーのダウンジャケットを羽織る。これは収納袋つきで小さくまとまるので重宝しているアウターだった。
洗面用具などの日用品はタイでも購入できるので、歯ブラシ、歯磨き粉、石鹸など有り物を荷物に詰めただけだった。T字の髭剃りに替刃、爪切り、耳かきだけは使い慣れた日本製品を持参した。胃腸系が弱い僕は日本にいる時に正露丸や整腸剤を常備していたが、それも気候や病原菌の違うタイでは役に立たないだろうと持っていくのを止めた。
あとは筆記用具にノート数冊、愛用品であるSEIKO(逆輸入モデル)の時計二つにカシオのGショック、タイで購入した安価なタイ製の携帯電話、解約して使えなくなる携帯電話もアドレス帳代わりに持参した。電化製品の類は電圧が違うタイでは使えないので全て諦めていた。当時はまだ変圧器という便利なグッズがあることなど知らなかったし、海外対応機器なんてものがあったかどうかも定かではない。いや、あったとしてもわざわざ電気屋に出向いて探すなんて事はしなかっただろう。
それでも音楽好きの僕にとって音楽のない生活は考えられない、俗に言う「ノーミュージック・ノーライフ」であったから、電池式のポータブルCDプレーヤーとウォークマンだけは処分せずに取っておいた。2000枚近くあった音楽コレクションで僕が買取業者に唯一売らなかったのが、ブルーハーツのCDアルバム3枚だった。それは僕が中学時代に音楽を聴き始めた原点のようなもので、そんな思い出の一品を数百円で手放すことだけはどうしても躊躇われたからだ。敬愛するヒロト&マーシーが次に組んだバンド、ハイロウズのCD等も一通りあったが、彼らの原点でもあるブルーハーツの初期アルバム3枚だけは安易に売ることなど出来なかった。その3枚はポータブルCDプレーヤーと共に海を渡ることになった。
あとは活字である。タイに住むようになれば必ず日本語に餓えることになるだろうとは容易に想像できた。だから大切な書籍だけは売らずに取っておいたのだ。それは当時の僕(若造)にとっての人生指南本のような数冊であった。
先ずは「一夢庵風流記(隆慶一郎)」。これは中学時代にはまった少年ジャンプに連載されていた「花の慶次」の原作で、戦国時代~江戸時代にかけて天下の傾奇者(かぶきもの)として知られた前田慶次郎の歴史小説である。派手な装いと異様な振る舞いで京を沸かせた傾奇者、いざ戦に繰り出せば朱色の長槍で一人敵陣を蹴散らす豪傑ないくさ人、当代きっての風流人でもあり、自由を愛するさすらい人でもある。そんな今で言うアウトローのような慶次の生き様に憧れを抱き、僕がこれまで何度なく読み返している愛読書である。
学生時代に旅仲間の友達からもらった「千年旅人(辻仁成)」もどうしても捨てられない一冊だった。三篇からなる小説であるが、僕が特に気に入っているのは本編ではなく、最後に書かれている数ページのあとがきだった。そこには以下のような文章がある。
肉体は船だとしよう。人間の魂はこっちからむこうへと渡るために肉体という船が必要なのだ。一生とは対岸までの川の幅に過ぎない。短かろうが、長かろうが、むこうへ渡る行為に変わりはない。どこが違うかと言えば、その渡り方ぐらいのものだ。どこをどう渡っても一生であることには変わりない。(中略)
通常、人間はこっちの岸からむこう岸へとまっすぐ川を渡ろうとする。ところが千年旅人と呼ばれる人々は川を単純に横断するのではなく、流れに乗って川を下る人々なのである。適当なところまで流されて、人生を多く堪能したのち、反対側へと上陸するようだ。生きているのはふつうの人と同じ川の流れの上なのだが、流れに逆らうのではなく流れに乗っているので時間とは無縁に多くの人生経験をすることができるらしい。
(引用:千年旅人 辻仁成)
この千年旅人という言葉の響きと、人生を例える言い回しがなるほどなと実にしっくりきて、自分も人生という荒波を流れ流され、様々な経験をしながら生きていきたい。千年旅人と呼ばれるような類の生き方をしたいと思ったのだった。
子供の頃は本を読むことなど皆無に等しかったが、自由な時間があった学生時代から幾らか本を読むようになった。とはいえ文学的な小説など頭が痛くなるばかりで、それは映画で十分だった。どちらかというとサブカル系や自己啓発ものばかりだった。要は手にとって簡単に読めそうなことが重要だった。よく通った本屋は新宿の紀伊国屋、渋谷のブックファースト、それと住まいのある下北沢にあったヴィレッジヴァンガードだった。特にヴィレッジヴァンガードには雑貨から一種変わったタイプの本まで様々置いてあり、長居しても飽きない大人のおもちゃ箱のような雰囲気の店だった。
そこで購入して気に入ったのがインディアン少年の物語を綴った「リトル・トリー(フォレスト・カーター)」や童話「モモ(ミヒャエル・エンデ)」などである。特に鬱屈していたサラリーマン時分に手にしたモモはしんみり心に染み入るファンタジー小説だった。「時間どろぼう」である灰色の男たちと息苦しさを感じていた日本の社会構造を重ね合わせ、まさに時間に追われるように日々淡々と仕事に明け暮れている自分の境遇に酷く嫌気が差したものだった。
人間が作り出した時間という概念とはいったい何なのか?それをまざまざと思い知らされるような作品で、「このままじゃ、ベルトコンベアに乗せられた商品のように画一的で平坦な人生があっという間に過ぎ去ってしまうのではないか…」と当時抱いていた焦燥感に活を入れられたような気分だった。
そして、自分の存在価値を憂い人生の方向性など全く定まっていない若輩者であった僕に、一筋の光とも言うべき希望のような指針を与えてくれた存在がロバート・ハリスだった。それは何か答えを捜し求めていた時に丁度いいタイミングで出会ってしまったという感覚だった。忘れもしない渋谷のブックファーストでふと目に止まった平積みされたコーナーの一角、サングラスをかけた男のニヒルな表情、見るからに怪しげな表紙とタイトル。エグザイルス?ギャング?
店員がオススメするように立てかけてあった一冊のハードカバーを手に取り、中をパラパラめくると、旅、ヒッピー、ドラッグ、ギャンブルといった興味をそそる言葉が並んでいた。少し読み始めたところですぐに夢中になり、並べてあった関連書籍の「エグザイルス」、「エグザイルス・ギャング」、「ワイルドサイドを歩け」など全て購入した。それは僕の趣味にどんぴしゃのロックンロールな格好いい大人の男の生き様が綴られた自叙伝であった。しかも僕の父親と同年代である。こんな素敵な大人が世の中にはいたのかと僕は忽ちファンになり、至極影響されることになった。
それからバーテンのジョーさんにもらった高橋歩の「LOVE&FREE」。
ガイド本はすでに持っていた地球の歩き方(タイ版)と(カンボジア版)の2冊。それに「指さし会話帳(タイ版)」と「タイ語基本単語集2000」の2冊をタイ語の勉強用にと新たに購入した。以上10冊程度をタイに持参することになった。
2003年1月15日の早朝、ついに僕はタイへ向け、長年住み慣れたアパートを後にした。
ドアを閉め、備え付けのポストに鍵を投函すると、表札代わりに貼っていたアルファベットの名前入りテプラシールを剥がした。ひんやりと冷たい朝の空気が、いざ南国へ向け旅立とうとしている浮き立つような気分を心なしか感傷的にさせる。何度となく歩いた駅までの数分間の道のり、様々な思い出や記憶たちがフラッシュバックのように頭の中に駆け巡った。
始発に近い早い時間であったが、小田急線のホームはすでに通勤ラッシュの様相を呈し、画一的なスーツ姿のサラリーマンで混雑していた。これが最後になるかもしれないと覚悟を決めるように、大きなバックパックとボストンバッグを前方に抱え込み、その荷物で隙間のない人混みを押し込むように満員の電車に乗り込んだ。そこにいた人々はどう見ても浮いた存在と恰好の僕を横目で見て、幾分うんざりするような視線を投げかけてくる。
ガタンゴトンと電車が揺れる度に人波に押されて、無理やり地面に置いたバックパックは僕の手元を離れて、足の踏み場もないスペースで居心地悪そうに居座っている。アウェイに乗り込んだサッカー選手はこんな気分なのだろうか。全てが敵に見えてくる。新宿まで少しの間の辛抱だ。僕は周囲から浴びせられる怪訝な視線を感じながら、思いをはるか南西のタイへと向けた。
それらを振り払うように、胸の内で一人口ずさむ。
「満員電車の中 くたびれた顔をして 夕刊フジを読みながら 老いぼれてくのはごめんだ……」
ブルーハーツの「ラインを越えて」という曲でマーシーが叫ぶように歌う、反骨のメロディー。
新宿に到着し、成田エクスプレスが出ているホームに行くと、ようやく同じような旅行者たちの姿を目にして少し安堵した。
成田空港で待ち合わせしていたリュウさんに数日ぶりに会うと、思いはすぐにタイ一点に切り替わった。
タイまでの移動の6時間、僕は購入してきたタイ語の本を取り出し、リュウさんに簡単な文法や発音を教えてもらいながらタイ語の勉強を始めた。タイに到着するまでに一通り本に目を通すと、日常会話に使えそうな50個程度の単語を書き出し、ノートを破った紙切れにメモした。
それが僕のタイ語の勉強開始と共に、タイ移住の第一歩となった。
タイ移住生活14年間の放浪物語―フィクション50%+ノンフィクション50%=(ハーフ&ハーフ)ストーリー