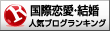> 登場人物

人生とはままならないものである。2500年前に悟りの境地に達した仏陀は言った。人生とは苦を背負って生きていくものであり、無常であると―。いくら自分があがき、もがき、努力したつもりでも、人生というものは己の思い通りには中々進んでいかないものだ。
人間は自分一人では生きていくこともできないし、そもそも二人の男女から生まれた時点で一人ではない。他人や社会や国家や時代という大小さまざまな波に翻弄され、生きていく我々は全くもって一人ではない。
そして、人生は選択の連続とも言うけれども、果たしてどれほどの割合で自分が決断してきたといえるものなのか。思い返せば、これまでの僕の人生は自ら流れるというよりは、むしろ流されてばかりの、もはや後戻りすら出来ない迷路のような道のりであった。あの日から、糸が千切れてしまった凧のように、行き先も知らずフラフラと風任せ、流されるままに歩んできた道のりであった。
「ヒロ君、そういうことなら今度、気分転換に日本を離れてアジアにでも出かけませんか。タイもいいけどカンボジアも面白いですよ…」
あの年の晩秋、登校拒否する子供のように勢いに任せて勤めていた会社を辞め、数ヶ月もの間、夢遊病患者のように、あてもなく都会の雑踏で彷徨っていた僕は、事情を聞いたタイ好き仲間のエビスさんに誘われるまま、タイ行きの航空券を購入した。
エビスさんとは、僕がタイに一人で遊びに行っていた頃にパタヤで知り合って以来の仲で、僕が日本で唯一頼れるタイ事情に精通したタイ好きの先輩でもあった。エビスさんも僕と同様、20代前半でアジアを知り、その混沌とした猥雑さにはまった口で、彼はタイに住みたいという理由で、仕事でタイに行ける会社を探し出し、就職した。
それは1990年初頭の頃だから、格安航空券という言葉がようやく世の中に認知され始めた時代である。彼は都内の雑居ビルに小さな事務所を構える旅行代理店に首尾よく転がり込むと、その数年後には晴れてバンコク支店での駐在員という立場を手にした。
会社からのバックアップで仕事と両立して現地のタイ語学校に通わせてもらったエビスさんは、若さから来るアジアへの情熱も手伝ってか、すぐにタイ語を覚え、数年後には隣国のカンボジア支店の立ち上げを任される存在までになった。まだポルポト時代の闇が国全体を覆い、街には土埃が舞い散り、貧困と犯罪がそこかしこに広がる無法地帯のような時代であった。
タイ、カンボジア両国で旅行業務に勤しみ、念願のアジア暮らしを満喫していたエビスさんだったが、まだアジア旅行自体が世間一般に浸透していなかったこともあり、数年後には赤字経営で現地支店は閉鎖の憂き目に遭い、エビスさんは敢えなく日本帰国を余儀なくされた。それから違う業種へ転職したエビスさんは、まとまった休暇が取れれば、再び旅行者として一人でタイを訪れるようになった。僕とパタヤで出会ったのはそんな時だった。
「こんばんはー、日本の方ですか?パタヤに一人旅なんて珍しいですね…」
僕は、その頃、ジョイという名前のタイ人女性に少なからず恋愛感情を抱いていて、会社の長期休暇を利用して、数日間パタヤを訪れていた。彼女が働いていたバービア(ビアバー)と呼ばれるオープンエア形式の屋外バーのカウンター席に陣取り、強くもない酒を煽り、彼女と四目並べゲームに興じていた時だった。
「ああ、はい、そうですが…」
旅先とはいえ、人見知りの僕は、今まさにナイトバーで目尻を下げて現地女性と戯れている姿を同じ日本人に見られてしまったことに恥ずかしさを感じ、決して自分の素性を知られてはなるまいと、そっけない口調で返事したつもりだったが、ニコニコと屈託なく笑いかけてくるエビスさんは、逆に同胞を見つけたとばかりに、無邪気な子供のようにグイグイと僕との距離を詰めてくるのであった。
この出会いをきっかけに、僕は日本に帰国してからもエビスさんと連絡を取り合い、タイへの思いを穴埋めするように、二人で会う機会も増えていった。仕事終わりに新宿アルタ前で待ち合わせて、エビスさん行きつけのタイ料理屋に連れて行ってもらう。タイでは100バーツ(約300円)にも満たないトムヤムクンが日本では1,000円以上することに驚き、日本という環境(気候)で飲むシンハービールは不味いことを知った。
その店の常連客なのか、いかにも夜の仕事で日本に来たであろうケバい服装と厚化粧のタイ人女性に片言の日本語で声をかけられ、嬉々としてタイ話に花を咲かせたが、その一方で彼女の肩口から滲みでる陰鬱な影のようなものに、なぜ彼女は日本に働きに来たのだろうかとふと思いを馳せ、切ない気分に駆られた。
タイマニアが集まるサークルのような親睦会に二人で紛れ込んだこともあった。クラブを貸しきって催されているその会合では、男女比半々ぐらいの大学生を中心とした若者たちが、それぞれグラス片手にタイ談義に興じ、店内から流れる大音響のタイミュージックに腰を揺らし、いかにもタイ好き専門のクラブといった様相だ。人見知りな僕も場の空気に後押しされ勇気を振り絞って声をかけてみる。
しかし、僕が発する「パタヤが好きで…」という言葉に対し、皆一様に距離をおくような素っ気無い反応。そりゃそうだ。彼らの口からは大学で留学とか、NGOとか、健全な話題がごく当たり前のように飛び交い、まったくもって僕らはその場においてお門違いの余所者であり、どちらかといえば軽蔑される対象であった。それでも僕は、東京という街でタイを味わえる機会があれば、喜び進んでエビスさんの誘いに応じた。
ゴールデンウィーク時期に代々木公園で開催されるタイフェスティバル。そこで初めてエビスさんの奥さんを紹介された。彼女もまたタイ好きの部類で、元々二人はアジアで知り合った旅仲間だった。子供はおらず共働きを続ける彼ら夫婦の思いは一つ、50歳までに二人で3,000万円を目標に貯金し、早めのリタイア。それからタイへ移住してのんびり老後をアジアで満喫するというものだった。
そんなに先のことまで計画を立てているのかと僕は衝撃を覚えたが、数十年先の未来に向けて今を我慢して日々コツコツと貯蓄していくなど、僕には途方もない作業のように思われ、まったく現実離れした考え方であった。
ただでさえ、東京での仕事に追われる毎日に嫌気が差していた。
タイ移住に向けて夫婦で協力し、堅実に今という時間を積み重ねている二人が羨ましくもあり、将来の計画など全くなく、自分がどうなりたいか、どうありたいかすら答えが出ていない僕は、諦めにも似た不安感と焦燥感に支配されていた。
人生とはままならないものである。
とはいえ、人生とは分からないものだ。
海外移住などという大それた考えは僕の中には存在していないはずだった。
ただ、現実から逃げたかった。
仕事を辞め、都会での存在理由を失った僕は、東京から逃げ出したかった。
自分探しの旅などという余裕すらなかった。
ただ、日本という国から離れたかったのだ。
そして、僕はエビスさんに誘われるまま、再びタイの地に足を踏み入れた。
タイ移住生活14年間の放浪物語―フィクション50%+ノンフィクション50%=(ハーフ&ハーフ)ストーリー