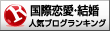僕の住むアパートの近くに、ひいきにしている、あるソムタムの屋台がある。毎日、昼過ぎになると、どこからやってきているのであろうか。重い屋台を引き、歩いてやって来る、丸々太った、かっぷくのいいオバちゃん。コラート出身ということは知っているが、その他のことは何も知らない。僕は、オバちゃんのことを、親しみを込めて「メ~(お母さん)」と呼んだ。
たまに、彼女と行っては「ソムタム・サイ・プーパラー・マイコイペットマーク(カニ・魚の塩漬け入り、あまり辛くしないでね)」といつものメニューに、カオニャオ(もち米)を頼むのが、お決まりのコースである。
そして、今や、ソムタム党を語るほど、ソムタムにイカれている僕は(ホンマかいな)オバちゃんのパパイヤを細かくカットしていく鮮やかなナイフさばきと、微妙な味かげんを調味する手つき、寸分の狂いもなく、すり鉢へと均等に振り下ろされていく木棒の行方に何度となく目を奪われることとなる。
「トン!トン!トン!」。小気味よく、辺りに響き渡る音の調べ。「これが、芸術だぁ~!」。とまではいかないが、僕はこのオバちゃんとソムタム音が織り成す景色が大好きである。
「メ~、サバイディーマイ?(お母さん、元気?)」から始まり、いつものやつを頼んだ後は、彼女の作業に目を奪われつつも、雑談が始まる。そして、メ~の作るソムタムを食べる回数が増えるとともに、雑談の内容も、彼女の私的なこと(例えば、子供がいるかとか、旦那がいるかなど)にも、当然及ぶようになった。
そして、ある日、僕は、メ~の口から、衝撃の告白を聞くことになる。なんと、彼女が、パタヤにやって来たのは、今から20年以上も前のこと。20歳で来たとしても、今は、40代の歳のはずだ。どんな苦労を背負ってきたのかは知らないが、メ~は、40代という年齢よりも、幾分老けて見えた。
そんなわけはないが、核心をつく質問を投げかけてみる。「メ~は、もうずっとここでソムタム売りをやっているの?」。「いや、私が、パタヤにやって来たのは、親(今はもう死んでいないけど)のために田舎に家を建ててあげるためだったのヨ。こう見えても、昔は、●×GOGOバーのナンバー娘だなんて言われていたんだから…」。
「え~!!」。まさか、こんなプクプクと太った肉ダンゴのようなオバちゃんが、たとえ昔だとしても、GOGOバーで働いていたなんて。今や、見る影もないが、いや、そういえば、メ~は愛くるしい目つきをしている。「へ~、そうだったんだぁ~」。衝撃の告白に勢い付いたのか、メ~の口は、そこから止まらなくなっていった。
「当時はね、ある時期になると、アメリカ軍の海兵さんたちが乗る船が、何隻も連なって、パタヤ湾沖に停泊するの。そこから、何十人もの金髪の外人さんたちが、小船に乗って上陸してきてね。私らは、それを見てヤンヤヤンヤの大騒ぎ。そりゃ、初めは知らない国の大男たちに戸惑ったけど、皆、たくさんチップをくれるし、優しい人たちもいっぱいいたしね」。
メ~は当時の思い出を懐かしむように、一言一言かみしめるように、口を開いていった。「今や、パタヤもこんな街になってしまったけど、昔は、それが年に何度かの恒例行事で、言わば祭りのようなものでね」。「へ~、パタヤにも、そんな時代があったんだ」。「トン!トン!トン!」というソムタム音は、あいかわらず小気味よく鳴り響いている。
「私達は体を張って仕事をしていたのヨ。小遣い稼ぎや、遊びの金欲しさだけに身体を売っているような今の女の子たちとは分けが違うわ。まあ、今の子全てがそうだとは言わないけど、少なくとも、私達には、今の子たちよりもプライドがあった。田舎の家族や子供のために、本気でお金を稼ぎたいと思っている人たちが、ほとんどだったし、そう思うからには、最善の努力、サービスを一晩を共にする相手に捧げたものヨ」。
彼女の真実味のある深い一言一言の前に、僕は熱心に耳を傾けるだけであった。「そうなれば、一夜の恋も何とかってやつで、やっぱり本気で恋をして、次は結婚。外国に行くような人も、少なくはなかったワ」。「まあ、そうなるよね。で、メ~は、そんな相手が見付からなかったの」。「私は、とにかく、お金を稼ぎ、田舎に送金するというだけで、頭の中がいっぱいだった。確かに結婚を申し出てくれた人もいたにはいたけど。やはり、私もまだ若かったし、そこまで踏み切る勇気がなくてね。それに、たくさんの男達にチヤホヤと優しくされて、お金までもらえる生活に、甘えていたのかもしれない」。
「そう、、もし、あの時、彼と―」。そう最後に一言ぽつりと言うと、メ~のほほに涙がつたった。昔、恋をしたファラン(外人)のことを思い出しているのだろうか。「今、旦那さんはいないの?」。メ~の涙には、気づかぬふりをして、僕は尋ねた。「当時、私がパタヤに来たばかりの頃に知り合ったのが、今の旦那。女好きでどうしようもない男だったけど、右も左も分からない田舎から出てきたばかりの私でしょ。そりゃ、こんな仕事だったし、寂しい夜も、辛い思いもいっぱいしたワ。そんなときに優しくされてね。今となっては、仕事もろくにしないバカ者だって分かったけど。ま、くされ縁って感じよね」。メ~は、そう言うと、その愛くるしい目つきを潤ませながらも、はにかんで見せた。
「友達は、ほとんどが、外国へ行き、それぞれの恋人と結婚したワ。昔は、そういう時代だったのよ。失敗して、タイに戻ってきた人もいるって聞いたけど。あのときの仲間で、今でもパタヤにいるのは、私ぐらいじゃないかしらね」。僕には、返す言葉も、なぐさめの言葉も見当たらなかった。だって、当時には当時なりのやり方、そして思いがあっただろうし、何しろ、今こうやってソムタム棒を振るメ~も十分かっこいいと思うからだ。ただ、僕のまだ知らない20年以上前にも、また、それぞれの一夜物語は、恋物語へと発展し、存在したという事実に、深い関心を抱いた。
「そう、、もし、あの時、彼と―」。メ~の決断は、彼女にとって正しかったのだろうか。間違っていたのだろうか。ふと、しゃがんだ彼女に目線が移った。丸々と太った体つきには、到底似つかわしくもない、はちきれ破れそうなTシャツから腰のラインが、顔をのぞかせた。
「んっ?」。僕の驚きを発する一言と視線に、彼女は反応した。「あっ、これ。当時の習慣がまだ抜け切れなくてね。でも、案外、サバイサバイ(快適)で、気に入っているのヨ」。メ~は、顔を赤らめながら答えた。
40歳を越えた肥満体から顔をのぞかせたのは、まぎれもなく、真紅のTバックだった。僕は、そのとき彼女が売春婦としての歴史を歩んできたことを、改めて実感した。元売春婦のソムタム売り。これが、案外パタヤの哀愁ってやつかもしれない。
ただ、そんな思いも、しばらくすると、「トン!トン!トン!」という小気味よいソムタム音に、かき消されていくのであった・・・。