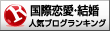リゾート地として知られるパタヤには、閑静で整頓されたジョムティエンビーチ、また、パタヤ湾からほどなく近い距離には、澄み切ったサンゴの海ラン島、パイ島などのアイランドも存在する。とはいえ、パタヤがB級と言われる所以は、とりわけGOGOバー、バービア、ディスコといったような夜の顔、歓楽街としての体を、存分に持っているからである。
パタヤでは、欧米人カップルや家族連れの姿をあまり見かけることは出来ない。自国でリタイヤした独身老人を筆頭に、何しろ世界各国の男たちが集う。一夜の恋、数日間のバカンス、擬似恋愛、本気の恋愛、老後の寂しい生活を穴埋めするため、、短期的、長期的とに分けられるが、まあ一言で言えば、男が女を求めにやってくる街、パタヤはそんな顔を存分に持っている。
そして、そんな街に降り立ってしまったタカ。彼は、決して金銭で一夜の相手を求めるためにパタヤを訪れたわけではない。街のほとんどの場所が、いわゆる、そのため(男が女を求めるため)に存在しているような感は否めないが、実際、パタヤには、それだけには留まらない哀愁だとか、全てを忘れさせてくれるような底抜けの明るさだとか、何とも言えない母性のような優しさだとかいったような雰囲気、オーラがあるのも確かである。
奇しくもタカが、はまってしまったのは、そんなパタヤだったのだろう。それは、イーグルスの名曲「ホテルカリフォルニア」の詩のように、一度訪れるとそこから抜け出せないという感覚。魔性的な魅惑の空間に堕ちていくといったような感覚に似ていた。タカにとって、パタヤはそんな街であった。そして、その魅惑の空間が、タカの凝り固まった夜の女性に対する懸念を振り払ったのだった。
帰国前日、タカは、アンを連れ出すことを決意した。いつもより早くに、場末バーへと足を運ぶタカ。夕方過ぎ、いつもと変わらない面々が、普段通りに出勤してくる。アンもその一人だった。だが、タカ一人だけが、いつもと違う自分を感じていた。
「タカ、サバイディーマイ?」。いつもと変わらぬ会話。すっかり定着した感のあるタカが座る所定の位置。そのカウンターの前にはアンが座る。そろそろ飽きてきた感のある四つ並べや、ビンゴなどのゲームに興じる。そして、バーに腰をすえ、頼んだハイネケンも底をつきそうになった頃合、タカはおもむろに口を開いた。
「アン。ワンニー、パイティアオ、ドゥワイ。ダイマイ?(アン、今日一緒に遊びに行ける?)」。ここ数週間の滞在で身につけたたどたどしい口調のタイ語でだった。アンは、何か決意めいたような表情をタカの顔から汲み取った。「えっ!いきなりどうしたのタカ?」。予期せぬことに驚いた様子のアン。
「いや、実は、明日、日本に帰らなくちゃいけないんだ。チケットももうすでに取ってあるし・・・」。「えっ、えっ、そうなの・・・。なんで急に・・・」。突然の連続に、動揺を隠せないアン。そして、そんなアンの対応は、彼女も少なからずタカに恋心を抱いていることを証明した。
「それに、、私と一緒に遊びに行くって・・・」。ともあれアンはバーで働く身。オフ代(連れ出し料)のことを言うべきなのかどうかを迷った。すかさず、タカが口を開く。「トゥデイ、ポム、ペイバー、アン。(今日、僕はアンをペイバーして連れ出すから)」。はっきりとした口調で、タカは答えた。
すっかり常連と化したタイ飯食堂に、アンを連れだって入るタカ。「あらっ、彼女?ナ~ラックだねぇ。(可愛いね)」。食堂を営むオバサンの冷やかしを受けながらもタカはまんざらでもない様子。タイで初めて食べる、他人との食事にタカは幸せ一杯だった。
そして、ちょうどパタヤの街も夕暮れ時を迎える頃、タカはある場所へとアンを誘った。そこは、パタヤ市内から数キロ離れた場所。レンタルバイクの後ろにアンを乗せる。心地よい南国の風が二人を包んだ。タカが見つけた秘密のお気に入りの場所。そこは、ある日、発見した丘を越えた所にあるプライベートビーチだった。そして、その地でのサンセット(夕暮れ)を見に、タカは一人でよく足を伸ばしていた。
「すごーい!きれーい!」。自分の住むパタヤとは思えない絶景にアンは嬉々と叫んだ。さっきまで轟々と照り輝いていた太陽は、ちょうど鮮やかなオレンジ色の夕日へと姿を変え始めている。
タカは、決して、アンに対する自分の気持ちを伝えることはしなかった。それは、旅行者としての自分と、異国のそれも夜の世界で働くアンの現実、、そのふたつを結びつけることが出来なかったからだ。傍らではしゃぐアンを、タカはただ黙って優しく見つめた。
そんなもどかしいタカの感情を汲み取ってしまったからだろうか。そして、アンも一人の女。実際、それに似た感情を彼女も抱いていたからだろうか。アンは、自分の仕事について、タカに語り始めた。
生まれ育った北の故郷。父母、兄弟、親戚、、アンは大家族だった。そして、アンには、幼くして身ごもった子供もいた。一族の砦として働き、その生計全てを担うアンの現実。まだ、28歳の彼女とはいえ、、タカは驚きで一杯だった。「今はお母さんが田舎で面倒を見てくれているんだけど・・・」。
アンは、財布から一枚の写真を取り出した。微笑むアンに抱かれる赤ちゃん。数年前の写真だろうか。そこには、今までタカには見せたこともない、母親の顔があった。そして、北の大地で生まれ育った彼女が、写真の中で身につけている衣服。それはいわゆる山岳民族の衣装といったほうがよかった。
「あっ!」。タカは、はっとした。タイに来るきっかけとなったあの笑顔。駅ビルの地下街でふと手にしたパンフレットの中の笑顔。意思の強そうな目とは逆に優しくゆるんだ口元。そこにあるのは、まさしく、タカが何となく引き込まれてしまったあの笑顔だった。
オレンジ色の夕日は、すでに、その半分以上を水平線へと沈めている。「アン、ポム、チョープ、クン。(アン、僕は君が好きだ)」。タカはアンに告げた。なぜか言葉は自然と口から出てきた。アンは何も言わず、ただそれに答えるように、ゆっくりとうなづいた。。
それから、二人は、目の前にある夕日をただ黙って見続けた。タカは、その夕日をずっと眺めていたかった。その二人きりの空間にずっと浸っていたかった。
しかし、しばらくすると残酷にも、オレンジ色に姿を変えた太陽は、そんな二人を知らぬとでもいうように、、そして、それがほんの一瞬の出来事であったかのように、、あっという間に暗闇の世界へと姿を消した。
それは、決してかなわぬ二人の淡い恋物語のようでもあった…。(完)