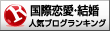もの凄い街外れ―。暗闇の田んぼのあぜ道を進んだところに1軒の民家はあった。看板なぞない店の名はチャーリーパブカラオケと言うらしい。「この店は特に特別だ」。このとき、おじさんが僕に告げたこの言葉の意味は分からなかった。一応、地元民のカラオケ施設みたいな感じの店内に入ると、女の子が6人、そして、奥の方に隠れるようにその子はいた。
恥ずかしいのか、積極的に言い寄ってくる他の子とは明らかに違う様子。年の頃は18~19歳、小柄で可愛らしい感じの子だった。よく見ると、どうやら目に小さな傷があり、それがコンプレックスのようだった。それに、よくは分からないんだけれど何か感じが違う。今までの子たちと何が違うのか、でも理由もなく僕を引き付ける。僕はその子を指名し、席に座るとビールを注文した。おじさんが何やらその子に話しかける。何を話したのかと聞くと、「お前のことだよ」と言った。
そして、あまり表情を変えないこの子に多少の興味を覚えつつも、会話もままならないままビールを1本飲み終えた僕は、「そろそろ帰ろうか」とおじさんに告げた。すると、この子も一緒にホテルに行くという。おじさん曰く、「やっぱりお前も、この子の目の傷が気になるんだろう?今連れて行かないなら、この子もきっとそう思うヨ。まぁ、でも慣れっこみたいだから気にはしなくてもいいけど」みたいな事を言ってきた。
「そんなこと思ってないよ、それは有り得ない」と必殺偽善者の血が騒いだ。いや、本当は理由が欲しかっただけなのかもしれない。しょうがなく連れて帰る事にすると、その子から初めて笑顔がこぼれ出た。「なんだよ?それ、やっぱり金かな。まぁ、たいした金額でもないし別にいいや」。おじさんは店から賄賂を貰うこともなく、ホテルまで一緒に戻ると、「明日この子を店まで送るように言われてるから、その時一緒に行こう。で、その後、市内観光ね」と翌日の予定を話し、僕らは部屋に戻った。
ドライバー兼通訳だったおじさんもいなくなり、二人だけの室内はしんと静まりかえり、通じない会話にかける言葉も見つからない。「うーむ、どうしよう。あっ、そうだ、ウォークマンに入っている日本のバラードでも彼女に聞かせて、少しでもムード作りを」。間が持たなくなった僕は、窓から夜景を眺めている彼女の耳元に、そっとイヤホンを近づけてみる。すると、彼女は照れ隠しなのか、おもむろにバラードの曲に合わせアップテンポのリズムを刻み始めた。
はにかみながら体を揺らすそのしぐさが妙に愛しく、思わず彼女を抱きしめたい衝動に駆られたが、当時の若い僕にはそんな余裕すらなく、「疲れたから先に寝るね」とそそくさ1人ベットの中に入るのだった。そして、しばらくすると、彼女も横に添い寝してきた。そこに会話は要らなかった。ただ、愛らしい彼女の顔を真っ直ぐ見つめたかったのだが、しきりに目の傷を気にしている様子だった。僕は、そこに静かにキスをした。「愛らしい君の顔を見つめさせて」と言葉には出来ないから。そして、結局2回戦の末、僕らは眠りについた…zzz)
目が覚めると昼前だった。先に起きていた彼女が無邪気な笑顔を投げかけてくる。ソンテウのおじさんと待ち合わせの時間、彼女を送りに再びチャーリーパブカラオケへ。先ほどまで笑顔だった彼女は、気のせいか少し暗い表情。店に着き、ママにこれから市内観光に行く旨を告げると、「マイも一緒に連れて行ってくれない?」と言われた。そして、「マイがアナタのことを気に入っているから」とも。
「はいはい、商売上手だねぇママさん」と心の中でつぶやきながらも、実際、僕の本音も同じくそうしたい。金額も大したことはない、ただ、実のところ彼女はどう思っているのか?まぁ、おじさん通訳で会話も何とかなるし、「一緒に行く?」と尋ねてみると、彼女から再び満面の笑みが返ってきた。「はぁ~、やられちゃってるかなーオレ。まぁいいや」とクールに対応するも心はルンルン気分♪そして彼女とおじさんを連れ、いざ市内観光に。
「洋服でも買ってあげようか?」とおじさんに聞いてもらうが要らないらしい。「食事は少しぐらい高くてもいいけど?」。その辺の屋台がいいらしい。うーむ、タイの女の子だったら買物してもらうのも稼ぎの内、違ったかなー。時が経つほど彼女の笑顔もどんどん増えてきている。そして、気がつくと僕は、ただ彼女の笑顔だけを探し夢中で追いかけていた。
夕食時になり、おじさんと僕は、又してもグデグデ加減に酔いどれ。おじさんは自慢げに「言った通りだろー!?」。それに対し「ハイ、言った通りです」と僕。「しかもなー、この子は何で高いもの買ってとか言わないか分かるか?」。「はぁー?」。「実は、その金で明日も明後日もお前と一緒に居たいんだと。洋服よりお前だと。お金もそんなに持ってないと言っといた。それになー、お前は日本で友達も彼女もいなくなって、一人ぼっち」。
そんな話をしたら、「私は彼の痛みが分かる。南のほうから売られてきて、家族とも離されずっと一人だった。でも今は店に行けば友達がいる。だけど、お前は今一人ぼっちだと。それに、お前、彼女の目のこと一言も聞かないらしいじゃない?まぁ、言葉しゃべれないから当然か、ははは…(笑)。あれは子供のときの虐待みたいだぞ。まぁ、気に入られてるなー。おじさんもお前のことは嫌いじゃないぞ、ビールおごってくれるしなー、ははは…(笑)」。
僕は、酔いがいっぺんに飛んでしまった。あの気丈ともいえる明るさは、そんな気持ちからきていたなんて。大体立場が違いすぎるじゃないか、売られてきて一人ぼっちにされた悲しみ(孤独)と、僕が自分でしでかした境遇(孤独)とでは。僕とおじさんの会話に無邪気に笑って、「うんうん」と意味も分からないのに頷く素振りを見せる彼女。洋服より僕なんかと一緒に居たいという彼女。部屋に戻ると、「明日は湖に行きたい」と絵を描き伝えてくる彼女。
その夜、彼女は1枚の写真を僕に見せてくれた。それは50歳ぐらいの欧米人で船乗りらしい。タイ南部のソンクラーにいたとき良くしてくれた人らしい。そして、明日は僕と湖で写真が撮りたいらしい。もちろん残り後2日、帰国前日まで彼女といるつもりだった僕は、「明日は湖に行こう!」と約束した。そして彼女は、眩しいほどの笑顔を見せてくれた。
翌日、ママに2日分の拘束費用を払い湖へ。山合いの中、神秘的な湖がそこにはあった。湖畔にはテーブルがあり、聞くとソンクラーの海にも似たようなものがあり憩いの場所だったようで、僕と一緒に来れてすごくうれしいそうだと、おじさんが通訳してくれた。湖畔に跳ね返る光に照らされた彼女は、神山の谷間から降臨した妖精のようだった。
そして、次の日の夜、日本帰国の瞬間(とき)はあっという間に訪れた。彼女の送迎はおじさんに頼み、ホテル前での別れだった。うつむいたままの彼女に笑顔は見当たらなかった。ただ、その目はキッ!と真っ直ぐ前だけを見つめ、力強く、いや思うに、こういう別れを何度かしてきたんであろう表情。僕は、次々湧き出てくる様々な感情をぐっと抑え噛みしめた。そして、言葉にしなくても、ただ心の中で誓った。「マイ、必ず戻ってくるから」と。
「マイ キットゥン レ ラックン ナ キットゥン マイ バーンナ」。帰国前夜、彼女は日本から電話してきてくれるなら、こう伝えれば私が出るからと僕に告げた。ただ、幾分タイ語が話せるようになった今改めて思い返せば、「マイはあなたが恋しい、そして、愛してる。マイを恋しいときは家に(電話して)」というような意味合いだったのかもしれない。
そして、当時の僕は、彼女の発音だけを頼りに書き綴ったそのメモを握り締め、全く意味も分からないまま、帰国後オウムのように繰り返し覚えては、国際電話をかける日々が続いた。まだ、片言のタイ語もしゃべれない26歳の若造だった―。
→後編へ
【文提供/ビレッジK氏】
アジアをこよなく愛し、通い続けること早や30年以上。自由の地を探し求め続けるオトコ(50代)。職業は「トレジャーハンター(自称)」。国境地とか辺境地とか危険な地帯が好き。大好物はビアチャーン。心はピュアな助べえオッサン日本A代表。好きな食べ物:もぎたてアジアの果実/嫌いな食べ物:都会で売れ残った渋い果実。