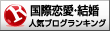「ヘイ、ガイズ(お前ら)!調子はどうだ?なんでも最近Tシャツのビジネスをスタートさせたらしいが…」
ニックから久しぶりに連絡があり、ジョージのバーに足を向けると、ニックは僕らに会うなりニヤニヤと嬉しそうに口を開いた。
「ハロー、リュウー、ヒロー。長い間見なかったわねー、元気にしてたー?」
カウンター席でニックの隣に寄り添うネンが流暢な英語で重ねて挨拶してくる。
「ワーオ、ネンって英語話すのうまくなったねー」
僕とリュウさんはしばらく見ない間に彼女の英会話力が格段にレベルアップしていることに驚く。しげしげと二人の様子を眺めながら、通りに面した軒先のカウンター席に並ぶように腰かけ、シンハービールを注文する。ニックとネンは相変わらず仲良くやっているようだ。意味ありげな笑みを浮かべながら、ニックが会話を始める。
「Tシャツ販売ならジョージが昔やってたらしいぞ。アメリカから大量にオーダーをもらって、Tシャツとかポロシャツ、フラッグなんかを製作していたようだ。パタヤの住まいにアメリカから取り寄せたプリントマシンがあって、古いけどまだ使えると言っていたが、もし必要なら彼に訊いてみるといい」
「ホントに?サンキュー!でも、Tシャツはナクルアのショップで漢字デザインのシルクスクリーンを作って、自分たちでハンドメイドでプリントしてるんだよね。この間、二人でバンコクに行ってサンプルの無地Tシャツを100枚ほど買ってきたんだ。だから、最近は二人で部屋にこもって作業に明け暮れてるんだけどねー」
流暢とはいえないが堂々とした口調のフランクな英語でリュウさんが答える。
「へぇー、それはグッドジョブだ。で、どこで売るつもりなんだ?日本向けのビジネスか?」
「いや、先ずはタイで売りたいと思ってるんだけどね」
「パタヤだったらショッピングモールのビッグCとかロイヤルガーデンの中にお土産ショップがあるだろう。ああいう多くのツーリストが集まりそうな店をレンタルするのがいいんじゃないのか」
「そうそう、あの屋台スタイルのお土産ショップね。でも、あの辺だと家賃が高いからさ。確か一ヶ月借りるのに2万とか3万バーツぐらいするんじゃなかったっけなー。以前いろいろと調べたことがあってね。まあ、場所を借りて売るなら、やっぱり市場がいいんじゃないかと思ってるんだよね。とりあえずはタイ人がターゲットだし、市場なら家賃も数千バーツ程と安いしね」
「そうか。マーケットといえばソイブアカオ辺りがいいんじゃないか。ほら、週に二度、火曜日と金曜日にやってる大型マーケットがあるだろう。サウスパタヤ通りの入口付近に出るやつだ。時々ネンと一緒に行くけど、彼女はあそこでよく洋服を買ってるよ」
「そうそう、俺もソイブアカオはいいと思ってるんだけどね。うちらの住まいからも近いしね。あと、テパシット通りに出る大型市場も考えてるんだよね。ニックは知ってる?ヒロ君は行ったことないんじゃないかなー。週末、金土日の三日間やってるナイトマーケットなんだけどね」
「ああ、場所はよく覚えていないけど知ってますよ。多分あそこじゃないかな。旅行者の時に夜のお姉ちゃんに連れて行ったもらったことがあるんですよね」
「そうなんだー。ちょっと遠いけど今度行ってみようか。実は昔あそこの市場でモノを売ろうとしたことがあってね。ケンちゃんって覚えてるでしょ?バンコクの日系企業で働いてる現地採用の彼。彼がパタヤに住んでた時にさ、一緒に何か日本の商品を市場で売ろうぜって話になってね。その時いろいろと調べたんだよねー」
「へぇー、そうだったんですね。で、何を売ろうとしてたんですか?」
「日本から古着の着物とか帯を持ってきて売ろうと考えてたんだけどね。ほら、市場でよくチャイナドレスとか売ってるじゃない。だからジャパニーズスタイルのキモノもイケるかもなんて思ってね。あそこの市場は普段はコンドミニアムの駐車場なんだよね。それを週末の夜だけロープで区分けして、テナントとして貸し出してるんだけど。でも、昔から商売してる業者たちの組合っていうか、縄張りみたいのがすでに出来上がってるんだよね。本来はコンドミニアムの事務所に行って、空いてる場所があれば借りられるんだけど、中々空いてなくてね。まあ、誰かしら古株が借り占めてるって感じかな。だから、俺ら外国人が現地業者の間に割り込んでいくとなると、又貸し、又又貸しみたいになって、吹っかけられちゃうんだよねー」
「なるほどなー。まあ、そう簡単にタイ人のテリトリーには侵入させないぞ!ってことですかね」
「まあ、そうなんだろうね。だから結構、通ってさー。あそこを取り仕切ってるようなオバサンまで行き着いて、うまく取り入って仲良くなってさ。ようやく借りられるところまでは話が進んだんだよね。市場は週末だけだから一日500~1,000バーツみたいな感じの契約でさ。広さは2メートル四方ぐらいだったっけなー。それで誰か売り子をしてくれるタイ人女性を探してたんだけど、なかなか見つからなくてね。だったらどこかの既存店と組んで委託販売するか、タイ人のふりして自分らでこそこそ隠れて売るかって話になったんだけど、そうこうするうちにケンちゃんがイモひいちゃってさー。それでオシマイ。それからしばらくして、彼は仕事を探すって言ってバンコクに行っちゃったんだよね…」
「へぇー、ケンさんとそんなことやってたんですね。でも、市場で自分たちで売るのはさすがにマズイんじゃないですかね。それって不法就労になりますよね?」
「まあ、やっぱり派手にやっちゃうとダメだよね。でも、昼間のパタヤビーチとか夜の繁華街でいろいろ売り歩いてる人たちいるでしょ。あれってタイ人じゃない、カンボジア人とかラオス人も紛れているんだよねー。彼らも言うなら我々と同じ外国人でしょ。あとさー、たまにインド人が街中で豆を売り歩いてるのとか見かけるじゃない。どう見てもバレバレって感じだけどさ。まあ、そこまでやれって話じゃないけど、初めは何でもグレーなところから試しに始めてみないと分からないし、そこからのスタートだからさー」
いつの間にか会話は僕ら二人の日本語だけになり、ニックはどこまで理解しているのか、その会話を楽しむように微笑を浮かべるだけだ。リュウさんはそれまでの話の内容を再度ニックに説明するように英語で言い直す。ニックがそれに答える。
「リュウの言ってることは分かるが、でも、お前ら気をつけろよ。この前、不法就労でファラン(欧米人)がポリスに捕まってたぞ。ちょうどその辺の通りでよく見かけてたんだがな。彼女だか嫁さんのタイ人女性がサイドカー仕様の屋台を引いてタイフードを売ってたんだけど、外国人の彼はそのバイクを運転したり、彼女の屋台仕事を一緒に手伝ったりしていたんだ。それを見た周りの同業者にでもチク(密告)られたんだろうが、連行されて、結局2万バーツの罰金を払わされたって話だ」
「えーっ、マジでー!?やっぱり簡単に捕まっちゃうんだ……」
パタヤでの商売に潜むリアルな現実に驚きを隠せない僕は、ジョージのバーの目前に広がる通りに目を向けながら、ニックの話に耳を傾ける。
「バービア経営でもレストラン経営でも同じだよ。ワークパーミットを所有していないと不法就労になっちまうんだ。オーナーだとしても店にいて客みたいに一緒に座って飲み食いするだけなら問題ないが、厨房を出入りしたり、スタッフに指示したりするのはダメなんだよ。まあ、そのラインが曖昧なんだけどな。だから結局、やられるのは誰かに邪魔者扱いされたり妬まれるようなパターンが多いらしい。これがタイスタイルってやつさ」
「そうなんだよなー。だから、バービアとか観光客が多いエリアで堂々とやっちゃうとダメなんだよね。それにファラン(欧米人)は目立つしね。俺らはタイ人と同じアジア系の風貌だから、そんなに目立たないと思うけどさー。まあ、市場でモノを売るぐらいなら、チクられない限りはバレないんじゃないかな。でも、気をつけないといけないけどね」
「そうですよね。でも、リュウさん、バービアで平気で売り歩いてるじゃないですかー?あれって大丈夫ですかね。もし捕まったら罰金ですよね?」
「それはもちろん俺も気をつけてるよ。実はさぁ、俺、アメリカに行った時に強制送還されてるんだよね」
「えーっ、マジっすかー!?」
「まだ言ってなかったけどさぁ。向こうのボクシングジムを点々と見て回ってたって話したよね。それでさー、最終的にLA(ロサンゼルス)のジムに落ち着いたんだけど。アパート借りてそこに通ってさぁ、トレーナーのライセンスを取得するためにベテランの黒人親父について色々教えてもらってたんだよね。それで、しばらくして自分を売り込むためっていうか自己紹介の挨拶用に名刺を作ったんだよ。財布に入れてたんだけどね。そしたら、ある日、ポリスから職質くらった時に財布の中を見られて、名刺を持ってるのは何か仕事をしてるんだろう?不法就労だ!って言われて捕まってさ。そのまま日本に強制送還だよ」
「そ、そんなことがあったんですか……」
「うん。あれは辛かったなぁ。だから、それ以来アメリカには行ってないんだよね。多分ブラックリストかなんかに載ってるだろうから、今行っても入国できないだろうけどね。確か10年経ったらまた行けるようになるんじゃないかぁ」
そう語った後、リュウさんはアメリカの入管事情を確認するようにニックに対し改めて英語で訊ねた。ニックは幾らか驚きの表情を見せながら、「多分そうだ(10年だったと思う)」と、半ば感心するようにリュウさんに応じる。僕が想像していた以上に、リュウさんは過去に色々と海外での場数を踏んでいるようだ。でも、それはアメリカで強制送還された経験があるからタイでは大丈夫だと言っているのか、二度とそんなことが起こらないように用心すると言っているのか、どちらに比重を置いているのか僕には理解できなかった。ただ、リュウさんの考えは「(最悪)多少の罰金は覚悟しながらも、強制送還されるようなことをしなければ大丈夫」という曖昧なものだった。
タイで長く生活していることでリュウさんが身につけた野性の感覚なのだろうか、それとも元々そういう性格なのか。いずれにせよ、それまで日本で全うなサラリーマン生活しか送ったことがない僕にとっては、その辺りの線引きが難しく、受け入れるのに戸惑った。やはり金もない人間が異国の地で這い上がっていくには、ギリギリのラインを攻めていかないといけないのか。いや、既に自分はもう日本社会をドロップアウトした旅行者の成れの果て、タイ沈没野郎ではないか。日本の友達に言わせるなら世捨て人の類だ。日々目減りしていく金以外に失うものはもう何もない。だったら泥臭いことでもやっていくしかないだろう?僕にそう思わせ洗脳するように、リュウさんは逞しい行動力で僕をグレーゾーンへと導いていった。
「俺は日本でも若い時によく揉め事を起こして警察にパクられてたからなぁ。まあ、前科はないから安心して」
「えー、そうなんですか……」
「うん。それにキャバクラで働いてる時は、やっぱり仕事柄いろいろとあったからね。うちの店、組関係の人たちもOKな店だったからさー。で、俺はプロボクサーだから用心棒じゃないけど、マネージャーを任されてたんだよね。夜の商売だから風営法も厳しいし、しょっちゅう警察から呼び出しを食らってたよ。だから警察の扱いには慣れてるっていうかね。まあ、でもタイではちゃんと気をつけてるから心配しないで。俺も強制送還だけは二度と勘弁だからさー。それに、万が一何かあった時は、一応こっちの実力者も知ってるからさー」
「へぇー、誰かタイ人に強力なコネでもあるんですか?」
「まぁね。実はさ、俺のスポンサーが医療器具メーカーの会社を経営している人だって前に話したよね。そのスポンサーのコネクションでバンコクの偉いドクターを紹介してもらったんだ。バンコクに住んでた時に時々挨拶しに行ってたんだけどね。で、俺がパタヤに来て、しばらくして、パタヤで何かの国際的なシンポジウムが開催されたんだけど、ドクターはその会合に出席するためにパタヤにやって来たんだ。それでパタヤの丘にあるロイヤルクリフって高級ホテルに呼ばれてさー。久しぶりにドクターに会ったんだけど、その時にパタヤの有力者を紹介してもらったんだよね。ほら、ダイアナホテルってあるじゃない。ソイダイアナって通りの名前になるだけあって歴史あるホテルなんだけど、あの辺の一体はダイアナグループが地主みたいなもんなんだよね。そのダイアナ系のエグゼクティブ・マネージャーだか偉い地位の人でさ、パタヤで何か困ったことがあったらいつでも連絡してくれってサイン付きの名刺をもらったんだよね。いつも財布の中に入れて持ち歩いてるんだけど。それ見せたらポリスに捕まっても大丈夫だからって言われたからさー」
「へぇー、それは頼もしいですねー」
「まあ、そういうものにあんまり頼っちゃいけないんだけど、何かトラブルが起きた場合に心強いからね。やっぱりここはタイで俺たちは外国人だからさ。コネクションがあるかないかで全然違うよ。まあ、だから何かきちんとしたビジネスが立ち上がればドクターに会いに一度バンコクまで挨拶しに行こうとは思ってるんだけどね。その時はもちろんヒロ君も一緒にね」
「はい、了解しました」
僕は"タイの実力者を知っている"というリュウさんの言葉に背中を後押しされるように、淡い野望を胸に抱きつつ、その言葉に酔いしれていた。ニックとネンの二人はそんな僕らの会話を微笑ましく見つめるだけだった。
日本人の若者二人が何やらパタヤでTシャツを作って売っているらしいぞ。そんな噂話が日本人長期滞在者の間でひっそり広まってしまったのか。作業に勤しむ毎日を送っていると、ほどなくして一件の問い合わせが僕らの元に届いた。それはパタヤの目抜き通りでマッサージ店を営む日本人オーナーからの問い合わせだった。
リュウさんは面識がある人物らしく、日本人長期滞在者たちが集うクッキーバーで事情を聞いた僕らは、早速その店に足を運んだ。大通りのセカンドロードで"TOKYO MASSAGE"という名前のタイマッサージ店を経営しているSさんは、大柄な体躯に豪快な笑顔を常に振りまいている人で、我々を歓迎するように挨拶してきた。年の頃は50歳を過ぎた辺りだろうか。
リュウさんの話では、Sさんは元々日本の金融業界で働いていたのだが、脱サラしてパタヤで知り合った女性とマッサージ業を始めたという。もう5年以上も営業を続けている旅行者に人気の店らしいが、実はSさん、パタヤに来た当初は100万円ほどの所持金しかなかったそうだ。そこから言葉も通じない異国の地で有り金を全てつぎ込み、自分が経験したことがない異業種のビジネスにチャレンジして成功を収めたのだ。
そのことを訊ねると、Sさんは「昔はまだパタヤも物価や地価が安かったし、物件の賃貸オーナーがいい人で、いまだに以前と同じ家賃で借りられているから、何とかやっていけてるんだよね」と経営の裏事情を教えてくれた。開店当初はタイ人の奥さんやスタッフたちと一緒に店の上階で生活していたようだ。
「なんか面白そうなことをやってる日本人の若者コンビがいるって話を聞いてね」。Sさんは僕らが作っている漢字Tシャツに興味を持ってくれたようだった。持参したサンプルTシャツを見せると、Sさんはデザインや素材などにはさほど関心を示さず、「幾らで売ってるの?よかったらうちの店の軒先で売ってみない?」とすぐに委託販売を提案してきた。とたんにリュウさんの顔つきが商売人みたく鋭い表情に変わる。
「Tシャツのボディーは2種類あるんですが、それとデザインやサイズによって200~250バーツに販売価格を設定しています。でもここは旅行者が多い通りだから300バーツで販売しても大丈夫だと思いますけどね。まあ、僕らとしては条件次第では委託販売もありかなとは考えているんですが」
「私は幾らで売ってもらっても構わないよ。実は店の営業時間はスタッフを椅子に座らせて軒先で客引きさせているんだけど、スペースが空いているから屋台なんかで貸してくれってよく言われるんだよね。でも、屋台に貸したら店先が汚れてしまうからね。だから勿体無いとは思っていたんだけどね。それで話を聞いて、君たちのTシャツを売ってみてはどうかなと思ってね。軒先にテーブルを並べて、その上に商品を並べておけば通りを行き交う観光客の目につくと思うんだよね。あとは客引きついでにうちのスタッフに売らせればいいわけだから。テーブルも丁度いいのが倉庫にあるから、よかったらそれを使うといい。場所代も要らないから、商品が売れた場合の何割かをこちらに払ってもらうっていう取り決めではどうかな?」
「それは売り上げですか?それとも純利益のパーセンテージですか?まあ、そうなると経費とか色々と計算が面倒なので、例えば、こういうのはどうでしょう。僕らは商品を一律200バーツで店に卸すような形で委託販売します。それをSさんが300バーツで売ろうが、500バーツで売ろうが、そちら次第です。いずれにせよ、商品を何枚か預けますので、売れたらその枚数分の売り上げから僕らの取り分をまとめて支払ってください。週ごとでも月ごとでも構いません。定期的にこちらに集金に伺いますので」
「うん。私はその条件でまったく構わないよ。じゃあ、早速よろしく頼むね。私は毎日店にいるから、いつでも来てくれて構わないよ。嫁とスタッフたちにも伝えておくから。それで、いつ頃から始められそうかな?」
「明日中にはまとまった枚数を用意してお届けします」
リュウさんは見事に委託販売の契約を取りつけた。僕の心はフワフワと浮つき小躍りしたい気分だった。ちょっとした幸運の波が僕らに押し寄せているように感じられた。
その足で僕らはさっそく準備に取り掛かった。僕の定宿があるソイダイアナからサードロードへと抜ける通り、ソイレンキーに衣料業者向けの用具専門店があった。そこでマネキンハンガーやハンガーラックなど、商品を展示しながら販売するためのアイテムを購入した。
こうして、僕らの作った漢字Tシャツは、パタヤの目抜き通りにあるタイマッサージ店の軒先で売られることになった。
突如として再び転がり始めた石ころ人生。
僕はパタヤという大海の荒波に揉まれる箱舟に乗り込んだような気分だった。
それは泥舟といってもよかった。
ただ、訪れる流れに刹那的に身を任せながら、南国の爽やかな風を感じていた。
タイ移住生活14年間の放浪物語―フィクション50%+ノンフィクション50%=(ハーフ&ハーフ)ストーリー