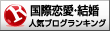パタヤに移住してから早や1年が経過した…。時間の流れや日付けの感覚などというものは、とうの昔に消えうせてしまった。だから、幾分肌寒い季節になってきたなと感じ、ふと気づくと年の瀬がやってきて、あれよという間に年を越して1年が過ぎていたという感覚だった。熱帯モンスーン気候に属するタイは、一年を通して平均30度近い温暖な気候が延々だらだらと続く。そんな変わり映えしない季節の中で日々暮らしているせいもあるのだろうか…。
タイでは乾季と呼ばれる11~2月頃が年間を通じて最も快適に過ごせる時季で、カラッとした天気の青空日和が続く。この期間は年末年始をまたいで観光客が最も多く訪れる繁忙期でもあるためハイシーズンとも言う。それから徐々に暑くなっていき、3~5月頃にかけて40度近い猛暑日が続く暑季が訪れる。4月といえばタイの旧正月、伝統行事ソンクラーン(水掛け祭り)がタイ各地で催される。人々はお祭り気分になって踊り騒ぎ、日照りの下、雨乞いの祈りを捧げて豊作を祈願し、新年を祝う。
そして、うだるような暑さに終わりを告げる雨がようやく降り始めると、それから6~10月頃にかけて長い雨季を迎える。とはいえ日本の梅雨時期のように連日シトシトと長時間に渡って冷たい雨が降り続くものではなく、生暖かく雨脚の強いスコールが短時間で大量にドバーッと降って、ピタリと止み、すぐに晴れ上がるといった感じだ。まさにバケツの水を一度にひっくり返したような雨である。だから、雨季とはいうものの、基本的には毎日暑いし、家に閉じこもりたくなるような気分でもない。言うなれば日本の真夏日(猛暑日)と夕立のような雰囲気で、外出時にスコールが来れば雨宿りして一休み…。それがタイ人の雨季の日常である。
そんなわけで、僕が実際に肌で感じる1年のサイクルを三段階で表現するなら、「今日も暑い、今日はやけに暑い、最近はとてつもなく暑い」そして、時々スコールといった具合である。春夏秋冬、メリハリがきいた四季折々の季節を感じながら育ち過ごしてきた日本人の僕にとって、タイでの暮らしは、毎日ムンムンとした熱帯特有(高温多湿)のサウナの中で過ごし、年がら年中、直射日光を全身に浴びながら、熱中症のように思考を飛ばされ続けているようなものであった。
そんな常夏の気候に身体を犯され毒され支配されて、僕の中にあった日本人的な感覚の全てはすでに過去のものになりつつあった。毎日決まりきった一日を繰り返すサラリーマン的な思考や価値観は、いつの間にか消えうせていた。もはや情熱的に生きるタイ人のように、刹那的に今を感じ、今を生きる、今日という一日を流れ流されるままに積み重ねるだけだった。ただ、将来に対する不安な想いが常に頭の片隅に居座っていたことだけが、日本人としての僕をわずかに主張しているようだった。
相変わらず貧乏生活が続いていた。日本から持参した手持ち資金はすでに底を尽きかけており、毎日の生活を厳しく節制し、やりくりしながら何とか生き残っているような日々の繰り返しだった。ジーンズやTシャツなどの衣類、それに靴(スニーカー)、時計など、日本から持参した数少ないブランド品(日本製の身の回り品)たちも、金目のものは全て市場や現地のショップに持ち込んで売り払い、生活費の足しにした。その代わりに、僕は市場に足繁く通い、古着(USED)を買うようになった。ソイボッカウ周辺~南パタヤにかけて市場が数箇所点在しており、毎週火曜日と金曜日の週二日、ソイボッカウの南パタヤ入口付近にできる大型市場は特に重宝した。僕が着用する衣服は、周りのタイ人みたいに安価なものばかりになり、見た目もすっかりタイ人と変貌しつつあった。
もちろん、毎日食べる食事は屋台のタイ飯が基本だった。スーパーで袋入りの即席麺やカップラーメンを買ってきて、それにツナ缶やアジ缶など缶詰の中身を入れて食べるのが、日本食をわずかに感じさせる僕なりのご馳走であった。超アクティブなリュウさんに毎日連れ出されるもんだから、酒浸りの日々も相変わらず続いていた。前日の深酒がたたって、いつも決まって昼過ぎ頃ようやく起床すると、飯食いがてら外出し、バイクの二ケツでパタヤの街をウロウロと徘徊する。そして、決まって日が暮れ始める夕方過ぎからバービア街に繰り出し、ハッピアワーやバイワン・ゲットワンフリーをやっている定番の格安店を回り、一杯30~35バーツ程度の最安タイウイスキー(コーラ割りwithライム)だけをひたすら飲み続ける。会計の際は、チップなどビタ一文置いていかず、たった5バーツのお釣りですら回収していた。呆れ返る店員にキーニャオ(ケチ)と言われようがお構いなしだった。
年末年始のハイシーズンになると、パタヤではあちこちの飲み屋でパーティーが催されるようになる。年越しカウントダウン時には、街中の至る所で一斉に花火が打ち上がり、爆竹が鳴り響き、通りは様々な人種が入り乱れた乱痴気騒ぎの様相になる。そして、年に一度の繁忙期だけに気前のいい金持ちファラン(欧米人)がそこかしこに溢れるようになる。バービアでは店内に常設してある"鐘を鳴らしたら店にいる皆に酒を奢らなければならない"という暗黙のルールがあるのだが、ハイシーズンになると、タイ人のお祭り気分に誘われて、ガンガン鐘を鳴らしまくって散財行動に走る酔いどれファランが出てくるので、そんな店を狙って探しては他人にたかるようにして酒を飲んでいた。風船を目印にパーティーが催されているバービアを見つけては、無料で提供される豚の丸焼きやチキン、カオパット(焼き飯)等タダ飯目当てに、盛り場を徘徊し練り歩くのが日課のようでもあった。そして、暇を持て余したアメリカ人の親友ニックから連絡が入ると、いつでもどこでもすぐに駆けつけて、彼から食事や酒を奢ってもらうのが常だった。そんなうだつの上がらない暮らしが続いていた。
唯一金を稼ぐための手段として立ち上げたホームページ、パタヤ便利屋コムから得られる収入は微々たるものだった。Tシャツ製作に始まり、豊胸クリーム販売、それにパタヤの現地案内、通訳、夜遊びガイド、送金代行、探偵調査などと、思いつくまま手当たり次第に、自分たちに出来そうなサービスをつらつらと掲載していたものの、これといった稼ぎ口はまだ見つからないままだった。たまに夜遊びガイドや送金代行などの依頼はあったが、それも直ぐに飲み代に消えてしまう程度の僅かなものだった。また、探偵調査も僕のわがままで終了して、無料の恋愛相談コーナーに変更してしまった。だから、実質、僕に入ってくる金銭はほぼ皆無に等しかった。そんな現状に対して不満は募る一方だったが、タウンハウスにタダで居候させてもらっている身分である以上、リュウさんにこちらから小遣いをねだることなど当然できなかった。そんな主従関係がはっきりと僕らの間にはあった。
あと半年も過ぎれば、おそらく手持ち資金もすっかり底をつき、俺は日本に帰国する羽目になるのだろうか…。最悪ニックに頼んで彼のレストランで働かせてもらうしかないのか…。いや、もう1年もタイで生活したのだから、これもまたいい経験になったんじゃないのか。そうなったらそうなったで仕方がないことだ、もう十分に楽しんだじゃないか。そう半ば諦めかけてきた頃だった…。
リュウさんが日本に一時帰国した。僕がタイに住み始めてからも、リュウさんは何度か日本に帰国していた。帰国のタイミングはだいたいビザが切れる時で、そのついでとばかりに、例のスポンサーに会いに行き、滞在資金を援助してもらってから戻ってきている様子だった。僕は独りタイに残されて、毎日あまり外出もせずに家に篭って悶々と考えることになった…。
そんなある日の昼下がり、ケンさんから久しぶりに連絡があった。どうやらリュウさんの携帯を鳴らしたが繋がらずに僕にかけてきた様子だった。ケンさんは現在バンコクの日系企業で現地採用として働いている。彼は元々バックパッカー上がりで数年かけてアジアを放浪した後、最終的に流れ着いたパタヤでリュウさんと知り合い、それから数ヶ月ほど同じ安アパートで一緒に住んでいたことがあるという話を聞いていた。
ケンさんはひと月かふた月に一度ぐらいの頻度でパタヤを訪れていた。会社からドライバーつきの車が支給されているらしく、いつも決まって自ら会社の車を運転してパタヤにやってきた。だから、そんな時は僕らもケンさんの車に乗り込み、三人で夜の街に繰り出していた。
リュウさんがいない時に、僕がケンさんと二人で会うのはその時が初めてのことだった。ケンさんは、僕が貧乏していることを気にかけてくれたのか、タウンハウスまで車で迎えにやって来て、奢ってやるからと日本食レストランのフジ(FUJI)に連れて行ってくれた。遠慮せずに何でも頼んでいいよと言われて、僕は少しだけ遠慮してサバの塩焼き定食を注文した。
「今日は朝から仕事でラヨーンに行ってて、その帰りなんだけど、君たちと一緒に飯でも食おうかなと思って、ついでにパタヤに寄ってみたんだけどね。リュウさんは日本に帰国中って電話で言ってたけど、いつ頃戻ってくる予定なの?」
「いやー、詳しくは分かりませんが、多分、一週間か二週間ぐらいだと思いますけど…」
「ふーん、彼も相変わらずだなぁ。それで今、君は一人タイに残されて、何か仕事でもやってるの?」
「いえいえ、大した仕事なんてしてないですよ。でも、何とか金を稼がなきゃ、もうそろそろヤバイ状況なので、ホームページの更新作業とか、メールチェックは毎日やってるんですが、そんなに依頼も来ないですしねぇ。まあ、リュウさんがいない間は何か依頼が来たとしても、僕一人では何も出来ないかと思いますが…」
そして、二人きりの食事が始まって、たわいもない世間話が一段落したところで、ケンさんはリュウさんがいる時には絶対しないような会話を僕にしてきた。
「リュウさんが一緒にいる時は、俺も詳しい話はあまり聞けなかったけどさ、何か二人でいろいろとやってるみたいだけど、今、君はちゃんと生活費を稼げてるの?彼から給料とかもらってるの?」
「いえいえ、まだ、ちゃんとした給料とかは出てないですよ。まだ、そこまで稼げてないので…。でも、今はタウンハウスにタダで住まわせてもらってますし、電気代とか水道代も全部払ってもらってますしね。もちろん商売関連でかかる費用も全てリュウさんに出してもらってますから。だから、まあ、僕はとにかく頑張るしかないんですけどね…」
「もしかして、リュウさんから一緒にビジネスをやろうよって誘われてさ、給料も払うから、なーんてことを言われて、タイ移住を決めたんじゃないの?」
「は、はい、、そうですけど…。なんで分かるんですか?」
「いや、実はね、俺も貧乏旅行の果てにパタヤで彼と知り合ってさ、あれこれ口説かれて一緒に住み始めたんだよね。君と同じような感じだよ。でも、結局、毎日、バービアで飲んだくれて、夢を語るばかりで、一向にビジネスなんて始める気配もないし、市場で日本のモノを売ってみようとか、そんな大して金にもならないインチキくさいことばかりやってたからさ。それで、ついには滞在資金がなくなってしまったから、もう駄目だと思って、彼の元を離れて、バンコクで現地採用の仕事を探したんだよね」
「えーっ、マジですか、そういう流れでケンさんはバンコクに行って再就職したんですね…。僕の場合は、日本に金持ちのスポンサーがいるから、彼に資金を出してもらって、日本食レストランかマッサージ店をやる予定なんだって話から始まって、生活できるだけの給料も払うから俺のビジネスを手伝わないかって、初めはそういう話だったんです…。でも、いざ僕が本気でタイ移住を決断した頃になると、リュウさんはやっぱり他のビジネスをやりたいからって話が変わって、それで結局、移住当初はタコライスの屋台をやろうという話になってたんですけど、その話もいつの間にか立ち消えになってしまって…。まあ、僕も、移住した当初は、タイのことを何も知らなかったですし、タイ語も全く話せなかったので。それにタイ人女性との恋に溺れたりして、どう見ても使えない人間だったので、まあ、しょうがないですよね。だから、文句は言えないっていうか。とりあえず先ずはタイに慣れることから始めて、早くタイ語を覚えて、僕が一人前になったら、本格的に何か一緒にやっていこう、スポンサーが納得するような何かイケそうなものができたら、ちゃんとした資金を出してもらえると思うからみたいな、今はそんな感じですかね…」
「そうそう、それって、まったく俺と同じパターンだよ。結局、彼は一人で何かをやるには寂しくて、誰かを道連れにしたいだけなんだと思うよ。そのスポンサーだって、俺にも同じような話をしていたけど、結局、何者なのか、本当に実在するのか、今でもよく分からないしね。だから、初めてリュウさんから君の事を紹介された時から、大丈夫かなぁって、ずっと気になってたんだよね」
「えっ、そうだったんですか、それはありがとうございます。実は、僕もタイに来て、しばらく経った頃、もしかしたらリュウさんは詐欺師みたいな人物で、自分は騙されているかもしれないって思ったことはあるんですよ。いまだに彼の素性が分からないと不信感を抱くこともあります。 でも、スポンサーの正体を訊ねたら、リュウさんの親戚のおじさんで、従業員が数千人規模の医療機器メーカーを経営している人物だっていう話ですし、 今は彼の言うことを基本的に信じるようにはしてるんですよ。確かに夢みたいな大きな話ばかりで、具体性のない、まったく実現しそうもない絵空事ばかり語って、うんざりする時もありますが、僕はリュウさんの野性的な行動力とか社交性に魅力を感じてるんですよね。初めは確かにインチキくさいと思ってましたが、でも、商売っていうものは、本来そういう原始的なところから始めることに意味があるのかもしれないっていうか。とにかく、まあ、やれることは何でもやってみようと思ってる感じですかね、今はそれだけです…」
「大丈夫?もう、すっかり彼に洗脳されちゃってるんじゃないの?まあ、第三者的立場というか、経験者の俺から見れば、君は彼に利用されてるだけっていうか、彼の孤独につき合わされてるだけだと思うよ。彼は意外に寂しがり屋だからね」
「はあ、でも、まあ、ここまできたら、もう別にどうでもいいんですよ。もし、騙されていたとしても、それは騙されていた僕が悪いわけですし。人を見る目がなく、頭が悪かったっていうだけの話です。まあ、このまま何事も成し得ることも出来ずに、金が尽きて、日本に帰国する羽目になっても、それはそれで仕方がないっていうか、自分が決めたことなので、諦められるっていうか…」
「そっか、まあ、君がそう思ってるんだったらしょうがないけど。でも、もし、金がなくなって、バンコクで就職先を見つけたくなったら、いつでも俺に言ってね。君は大学も出てるみたいだし、日本ではサラリーマンをやってたんだろう。俺みたいに先ずは現地採用からで良かったら、いくらでも紹介できるところはあると思うからさ。まあ、俺も早く駐在の立場になって、もっと稼がなきゃとは思ってるんだけどね。やっぱり安定感が違うからさ。だから、君も早く見切りをつけて、そういう生活に変えたほうが将来性があるとは思うけどね」
「はい、本当にありがとうございます。でも、今は、自分で金を稼げるようになるまで、何とかリュウさんと一緒に頑張ってみようと思ってます…」
ケンさんの口ぶりは、僕がリュウさんの元を一刻も早く離れて、自分と同じようにバンコクで働くほうが賢明だと、強く勧めてくるものだった。確かにバンコクで現地採用というのも悪くない考えだと思ったことはある。しかし、それだと日本でやってきたことと同じことの繰り返しだ。サラリーマンが嫌でタイに移住してきたのだから、それだけは絶対に勘弁だった…。
「何か商売のヒントになるかと思ってさ。いろいろとお土産を買ってきたよ!」
日本に一時帰国してから十日ほどで、リュウさんはタイに舞い戻ってきた。スポンサーへの金の無心が無事成功したのか、リュウさんは機嫌よく住まいのタウンハウスに帰還し、日本滞在中にあちこち回ってきたという営業談義をしながら、買ってきたお土産を全てリビングのテーブルの上に並べていった。
そのほとんどが100円ショップやディスカウントショップで購入してきたもので安価な商品ばかりだった。それは俗に言うアイデアグッズで、排水溝が詰まらないように装着する金網ネットなど、暮らしに役立ちそうな便利グッズ、生活雑貨だった。リュウさん曰く、この手の日本製アイデア商品を参考にして、タイで同じような商品をコピーして作る、あるいは日本から輸入して売るほうがいいのか、とにかくタイにはまだ無さそうなカテゴリーでヒットを狙うという案であった。なるほど、そういう考え方もあったのかと僕は納得した。
そして、Tシャツ製作に使えそうな文房具や道具類、簡易的な書道セット等を購入してきた。特に本屋で気に入って、つい買ってしまったというのが、二冊の分厚い書籍。その一冊は金魚の写真集で、もう一冊はブルース・リーの写真集だった。リュウさんは、これらの写真をデザインにプリントしたTシャツを作ろうと目論んでいる様子だった。僕も当然のように幼少時代ブルース・リーに憧れ真似して育った世代なので、映画のワンシーンなんかをそのままコピーしてプリントするか、アレンジして売るのはアリかもしれないと感じた。映画好きの僕は、東京で独り暮らしをしていた時、大好きな映画(主人公)のポスターやポストカードをコレクションのように買い集めては、アパートの壁にベタベタ貼りまくっていた。住まいがあった下北沢には、その手の趣味の店が沢山あった。
だから、僕は、日本の和を感じさせる金魚プリントのTシャツもタイで売るなら良さそうだけど、やっぱり日本向けで考えるならば、ブルース・リーのTシャツのほうがイケそうだと思い、キャラクター物とかヒーロー物が好きで欲しがるファンやマニアがいるんじゃないかと率直に感じた。その写真集に一通り目を通すと、いいイメージが次々に沸いてくるようだった。
「Don't Think, Feel!(考えるな、感じろ!)」
普及の名作「燃えよドラゴン」でブルース・リーが言った名セリフ。その言葉が僕らを導いていくような気分だった。
それから、僕とリュウさんは、さっそくTシャツ製作に取りかかった。映画の中に出てくる印象的な名シーンを切り取った写真(デザイン)を二人で選び、数種類ピックアップすると、久しぶりにナクルアのTシャツ工房を訪ねて、木枠のお手製シルクスクリーンを注文した。それが完成したら、それぞれ思い思いに、いろんな色のインクを使って手刷りプリント作業に明け暮れた。そうして一週間ほどして、50枚ほどの新作Tシャツが出来上がった。
すぐに僕は、インターネットでブルース・リー関連の店がないかと検索した。すると、日本全国各地に10~20店舗ほど、ブルース・リーのアイテムとか関連グッズを取り扱ってそうなマニア向けの専門店が見つかった。その中でメールアドレスが記載されている店の全てに、片っ端からダイレクトメール(DM)を送りつけてみた。
「私どもはタイで日本向けのTシャツ製作販売など様々な事業を展開しておりますパタヤ便利屋コムと申します。ブルース・リー関連のTシャツも取り扱っております。ご興味がありましたらご連絡ください」みたいな感じに…。
しばらく反応はなかったが、メールを一斉送信してから、一週間ほどが過ぎた頃だったろうか。ある業者から一通の返信があった。「興味があるのでぜひ商品を見てみたい。近いうちにタイに行く予定だから一度お会いしましょう。そのときサンプルを持参してください…」という当たりメールだった。10件近く送ったダイレクトメールの中で返ってきた、唯一の返信メールだった。
すぐに「了解いたしました。いつでもご連絡ください!」と返事を送ると、それから程なくして、その業者さんが本当にタイにやって来る話になった。僕らは、数日バンコクに滞在できるようにと荷造りをして、約束の当日、指定された場所へと足を向けた。そこはバンコク都心部のスクンビット・エリアにある、高級タイ料理の料亭風レストランだった。
そして、その後の僕らの運命を大きく変えていくきっかけとなる重要人物Tさんとの出会いの夜となった。
運命の流れを変えたのは、ブルース・リーだった。
タイ移住生活14年間の放浪物語―フィクション50%+ノンフィクション50%=(ハーフ&ハーフ)ストーリー